ジャン・ジャック・ルソーの『エミール』と二度目の誕生
一度目は、存在する為に。
二度目は、生きる為に。
上記の言葉は、十八世紀のフランスで活躍した思想家、ジャン・ジャック・ルソーの有名な著書『エミール』の一節、
『わたしたちは、いわば、二回この世に生まれる。一回目は存在するために、二回目は生きるために。はじめは人間に生まれ、つぎには男性か女性に生まれる』
をアレンジしたものです。
17歳の時、初めてこの言葉を知り、目の覚めるような思いでノートに書き付けました。
それが心の支えになり、18歳で家を出て就職した時、「二度目の誕生」を実感した次第です。
以下、ルソーの『エミール』について紹介します。
『エミール』と青年期の課題
『エミール(エミール、または教育について)』は、ルソー自身が家庭教師となり、エミールという架空の少年をいかに育て上げるか、小説のような形式で綴った教育書です。
著書は、五部構成になっており、それぞれの時期にふさわしい親と教育者の在り方を説いています。
- 第一編・・エミールが0歳からほぼ1歳頃までの、乳幼児期
- 第二編・・口がきけるようになる一歳頃から十二歳頃までの、児童期・少年前期
- 第三編・・十二歳頃から十五歳までの、少年後期
- 第四編・・十五歳から二十歳までの、思春期、青年期
- 第五編・・二十歳以降の、青年期最後の時期
『わたしたちは、いわば、二回この世に生まれる。一回目は存在するために、二回目は生きるために』は、第四期の思春期・青年期(十五歳~二十歳まで)に記された言葉で、この時期、自我を確立した青年は、自己に対する愛情を社会に向け、人類愛へと高めていくことが大切だと説きます。その根拠となるのは、他人に対する憐れみと、確固たる人生の指針であり、いわば自己実現が社会にとっても有益であることが理想というわけですね。
それについて、西 研氏は著書『NHK「100分de名著」ブックス ルソー エミール 自分のために生き、みんなのために生きる』の中で、次のように述べておられます。
エミールは十五歳までは、自分が快適に生きるための有用性で物事を理解するという、実用的でわかりやすい考え方でやってきました。
しかし成長するにつれて、宇宙を理解し、そこでの人間の地位を理解したいという欲求も出てくるでしょう。
そしてこの地位を理解したいという欲求も出てくるでしょう。
そしてこの地位を理解したいという欲求は、自分の生は何のためにあるのか、という「生きる意味の問い」に答えを求める、ということでもあるのです。ルソーはこれに対して、<人間はよいことをするために、神によってつくられた>という答えを出しました。
「よいこと」の意味について、ルソーは詳しく語っていませんが、一言で言えば、他人の幸福に寄与すること、といっていいでしょう。「わたしたちは幸福になりたいと思っているばかりではない。ほかの人の幸福も願っている。そして、ほかの人の幸福がけっして私たちの幸福のさまたげにならなければ、それはわたしたちの幸福をいっそう大きくする(中巻216ページ)」
他人の幸せにつながることをすることで、自分も幸せになる。そういう生き方をルソーは思い描いています。
「仕事」を考えてみても、お金を稼ぐことはもちろん大事ですが、やはりそれが誰かの役に立つとか、どこかで人びとの幸せにつながっていると思えることが、仕事を続けていくうえでの大事な支えになるのではないでしょうか。
自己中心の子どもから社会的存在になる
上記を分かりやすく喩えれば、「自己中心の子どもから社会的存在になる」ということです。
たとえば、ロボット作りが趣味の男の子がいたとします。
男の子は非常に優秀で、大学も有名な工学部に進学が決まりますが、ある時期から、好きなロボットを作るだけでは物足りない、自分は本当に凄いロボットが作れたら、それで満足なのかと自問自答するようになります。
それは、成長した男の子が、次には社会との関わりを求めるようになるからです。
「自分はロボットを作るのが好きだ。ロボット作りを一生の仕事にしたい」と志すのを自我の確立とするならば、「ロボット作りの才能を、どのように社会に生かすべきか」を考えるのが社会性です。
ロボットといっても、工業用ロボットから医療用ロボットまで、千差万別であり、漠然と「ロボットを作りたい」と思っても、それだけでは社会との関わりは出来ません。
「自分の祖父は片脚が不自由で、日常生活にも大変苦労した。同じ苦しみをもつ人の役に立ちたい」と医療用ロボットに興味をもつ人もあれば、「NASAの火星探査の映像に感動した。自分も宇宙開発に携わりたい」と壮大な夢を描く人もあるでしょう。
それが「自分を社会に生かす」ということです。
そして、実際に、ロボットを作ってみて、患者さんに感謝されたり、自身の設計したロボットが火星探査に使われて、深い充足感を覚えたり。
そうした体験の中で、人は社会的存在になっていくわけですね。
ちなみに、ドイツの哲学者、カール・マルクスは「人は労働を通して社会的存在になる」という名言を残しています。
今の世の中、労働というと、ブラック企業のような暗いイメージしかありませんが、人間の労働にも三種類あり、ここで喩えられるのは、自己実現としての WORK です。
好きなロボットを作って、それが誰かの役に立つ。
それこそが自己の完成であり、社会的体験です。
ルソーの言う、二度目の誕生とは、社会的な目覚めを意味しているわけですね。
自身で社会を意識して、社会からも受け入れられる。
この相互作用を欠いて、真の自立は有り得ません。
さらに歩みを進めて、次は命と文化の継承――すなわち、結婚と子育て――によって、生物学的な人生を全うするためにも、社会的存在としての自己を確立することが非常に重要なのです。
どんな人間も、生まれた時は、真っ新な赤ん坊で、快と不快しか知りません。
周りのことなどお構いなしに、泣きたい時に泣き、食べたい時に食べます。
しかし、心が発達し、自我が芽生えると、「自己とそれ以外」を意識するようになり、社会での手応えを求めるようになります。
その為には、「自分はどう生きたいのか」という指針が大事で、その答えに辿り着くまでが、十代の葛藤です。
人として、もう一度、この世に生まれ出るのですから、その苦しみも半端ないです。
もがいて、わめいて、のたうちまわって、やっと何かが見えてくるぐらい。
だからこそ、その答えを見つけた時の感動もひとしおです。
親の胎内から飛び出し、今度こそ本当に自分の目で世界を見るから、『二度目の誕生』と言います。
↓ こちらの解説本もおすすめ
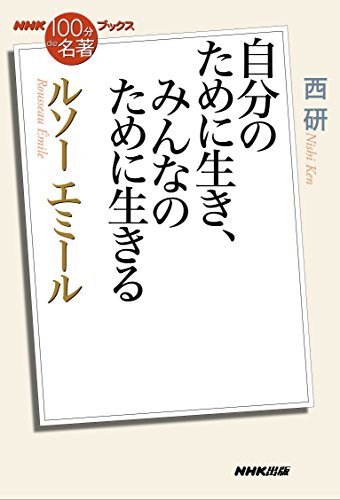
NHK「100分de名著」ブックス ルソー エミール 自分のために生き、みんなのために生きる Kindle版
『二度目の誕生』とは
このコラムは2020年に執筆しました。
『人は二度生まれる。一度目は存在する為に。二度目は生きる為に』は、私の大好きなジャン・ジャック・ルソーの言葉です。
私にとっては、十八歳の旅立ちが二度目の誕生でした。
二度目の誕生の意味は、恐らく、十代で自立した人にしか分からないと思います。
何故なら、進学を経て、二十代で自立した人は、『半分大人、半分子供』の状態で世に出ることになりますが、高校卒業後、すぐに家を出て、実社会に飛び込んだ十代は、子供の世界から一気に大人の世界に叩き込まれるからです。
私は後者のケースで、高校卒業から二週間後には寮生活と新人研修が始まったのですが、それまでご飯も、税金も、光熱費も、全て親任せだったのが、その日を境に一変、自分の一手に引き受けることになったのですから、最初は大変なプレッシャーでした。しかし、不安や恐れは数日もしないうちに、社会人の自覚に取って代わり、「人の生命を守る」という責任ある仕事を任されて、二度目の誕生を実感することができました。
当時の感慨を小説に書いたのが、後述の抜粋です。
ルソーの言葉を借りれば、一度目は肉体として生まれ、この世に存在するに過ぎないが、二度目はアイデンティティを確立して、自分の人生を生き始めます。
二度目の誕生を実感するには、自分が何ものかを知ることも大事ですが、自分自身の力で生活を立てて行くことも同じぐらい重要です。何故なら、この世に生きることは、ただ息をして、存在するだけでなく、社会の一因として関わっていくことが不可欠だからです。
子供のうちは、親に食べさせてもらって、存在するだけで生きて行けますが、自立する年頃になれば、社会における立ち位置、生活の手立てなど、それらもひっくるめて『自分』という人間を形成するようになります。カール・マルクスが『人間は労働を通して社会的存在になる』と著しているように、誰の人生も、社会との関わりをなくして成り立たないからです。
ある意味、二度目の誕生とは、家という殻から抜け出して、社会における自分の存在を認識することかもしれません。だから、その過程に躓くと、自己無価値感や無気力に陥り、家という殻から一歩も出られなくなるのかもしれません。
きょうだいが五人、十人といて、十代半ばにもなれば、一家の稼ぎ手として大人並みの働きを求められた時代と異なり、今はいつまでも子供で居ることができます。臍の緒を引きちぎっても、殻から出て行く勇気や行動力も昔ほどに求められません。また、社会においても、集団就職で上京した高卒者を企業が責任をもって面倒を見るような体力も残されてないのが現実です。
それでも「どう生きるか」は自分で選ぶことができますし、親子三代、一つ屋根の下で暮らしても、自立する人は自立しています。
現代には現代の『二度目の誕生』があり、それは真剣に考え抜いた人だけが辿り着ける境地ではないでしょうか。
どこで、どんな風に生きるにせよ、世界の光を見るには、親という殻を内側から突き破るほどの勢いと覚悟が必要です。
それが親の目には『反抗』と映るのです。
参考記事
『オイディプス王』と精神的な親殺しについて
青年が自立に際して親と対決する時、心の中で親殺しを成し遂げるかのような葛藤と衝動を感じることについて、ギリシャ神話の悲劇「オイディプス」になぞらえたコラムです。
精神的親殺しとは何か 子供の自立と親子対決 ~河合隼雄の著書【家族関係を考える】より
心理学者・河合隼雄氏の名著より、内的な親殺しに関する解説を紹介しています。
社会的存在としての人の生き方
最後に、西研氏の解説を紹介します。
エミールは15歳までは、自分が快適に生きるための有用性で物事を理解するという、実用的でわかりやすい考え方でやってきました。しかし成長するにつれて、宇宙を理解し、そこでの人間の地位を理解したいという欲求も出てくるでしょう。そしてこの地位を理解したいという欲求は、自分の生は何のためにあるのか、という「生きる意味の問い」に答えを求める、ということでもあるのです。
ルソーはこれに対して、<人間はよいことをするために、神によってつくられた>という答えを出しました。「よいこと」の意味について、ルソーは詳しく語っていませんが、一言でいえば、他人の幸福に寄与すること、といっていいでしょう。
≪中略≫
「生きる意味の問い」にはもう一つの面があります。<人生のなかで不遇な状況にあっても、やはり人としてなすべきことをして生きればよい。神様は必ずみていてくれる>。そういうメッセージもルソーの宗教論には含まれています。
人は愛する人たちがいることによって、また、自分が力を発揮した仕事を人びとが評価することによって、元気に生きていくことができます。そういうときには、あえて「生きる意味」を塔必要もないほどです。しかし人生のなかで、不遇な状況に直面することもあるかもしれない。そんな苦しいときにでも、まっすぐな気持ちをもって生きるためには神の信仰が必要だ、とルソーは考えていたのでしょう。
では、「不遇なときに、どうやってまっすぐに生きられるか」という問いを「神なし」でどう考えるか、この課題に立ち向かったのが、ルソーよりも百数十年後のドイツの哲学者ニーチェでした。彼が示したのは、<恨みや妬みは自分自身を貧しくする、ということを深く自覚したうえで、わずかであっても喜びのほうに自分を向けていく>という生き方です。この考え方が結晶したものが有名な「永遠回帰」の思想になるのですが、ここでは十分に解説する余裕がありません。
ちなみにぼく自身は、神様を信じることはできなくても、「人間の努力」を信じることはできると思っています。
西氏の解説にもあるように、どんな人間も、根本的に社会的存在であり、社会(他者)との関わりなしに、真の幸福は有り得ません。
多くの人が感じる生き辛さも、元を辿れば、「評価されない」「誰にも愛されない」といった、周りの無関心や否定的態度に起因します。
そう考えると、第二の誕生とは、「一度目は人間として生まれ、二度目は社会的に生まれる」と表すこともできるでしょう。
何にせよ、親の庇護を抜け出して、精神的にも、経済的にも、社会的にも自立することが、最初の一里塚であることは確かです。
そこに至るまでの過程が険しければ、険しいほど、卵の殻を破って、外に飛び出した時の感動もひとしおではないでしょうか。
【小説】 18歳の旅立ち
自由への憧れと「自分であること」への渇望
家を出る前に書きためたエッセーをベースにしています。
主人公は18歳の男の子。
『エル』と呼ばれる、顔よし・頭よし・家柄よし、の三拍子そろった有名建築家の父親に反発して、高校卒業と同時に家を出ます。好きな音楽の道を歩む為です。
ジャズ・ピアニストを目指して、ライブハウスのオーディションを受ける予定です。ちなみにエルは『曙光』の主人公、ヴァルター・フォーゲルの九代目の子孫にあたります。
彼と父親の葛藤は、芸術とは己の極限を目指すこと 映画『Shine』とラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番に掲載しています。
“その日”まで、俺は小さな殻の中の住人だった。
世界は既に存在していたけれど、まだ俺のものではなく、そこに含まれる様々な事象も、遠い影でしかなかった。
「生きること」への希求と、「自分であること」への渇望。
「自由」への憧れと、「未知なるもの」への不安。
世界はすぐそこにあるのに!
硬い殻が俺と世界とを阻んでいた。
ただ存在するだけなら、死んでいるのも同じこと。
無為に時を過ごすぐらいなら、いっそ時を飛び越えた方がましだ。
時は欲求だけをつのらせ、未知なるものへと心をいっそう掻き立てる。
気の滅入るような息苦しさの中で、俺はずっともがき続けた。
心満たす「何か」を必死に探しながら。
「何か」。
自分だけに与えられた「何か」。
それ無しには生きることも、存在することもできない、自分が自分である為の「何か」。
そんな何かに巡り会えたら、今すぐにもその一点に流れ出せるのに!
俺は必死に殻を叩き続け、ついに殻の“外”へと飛び出した。
自分だけを道連れに。
その瞬間の眩しさを、俺は生涯忘れない。
本当の意味で生き始めた、あの劇的な瞬間を。
見るもの、触れるもの、すべてが新しく、日々生まれ変わるような鮮烈な感動を。
世界は決して優しい場所ではないけれど、真摯に生きる者には必ず報いてくれるものだ。
自分を変える「何か」も、心から探し求めれば、いつか必ず巡り合える。
生は一瞬。そして世界は計り知れぬほど深く、広い。
同じ生きるなら、自ら立ち、自ら歩いて世界を渡ろう。
たとえ片翼の鳥になっても。
小説『三番街にピアノが鳴ったら』
頼るものも何もない町で、一人で、自力で生きていけるだろうか
ハイウェイの照明が、光の矢のように窓の外を流れていく。
彼はバスの窓枠に肘をかけ、ぼんやりと窓の外を見つめていた。
昼間は緑が映えた丘陵も、夜の中ではうねるような暗黒の波にみえる。
風も、光も、時間さえものみ込むような深い闇が海のように眼下をおおいつくしていた。
時折そのうねりの中に、壮麗な都会の輝きが垣間見えたが、その光もだんだんに遠ざかり、いつしか闇の向こうに消えていった。
昨日までの苦い思いも、嫌な出来事も、一切が時の彼方に過ぎていくみたいだ。
もう何も追って来るものはない。
ひとり、見知らぬ明日へとひた走ってゆく。
思えば、長い道程だった。
あの家に息苦しさを感じるようになってから、どれほど外の世界に飛び出すことを夢見てきただろう。
だが、彼の翼は父の手で幾度となくへし折られ、その度に鉄の鎖で縛られてきた。
そして、もう自分は飛べないのだと……どれほど自由に焦がれても、あの父には抗えないのだと諦めかけた時、奇跡のように橋がかかって、とうとうあの壁を飛び越えることが叶ったのだ。
それから勢いだけでここまで来たが、目的地に近付きつつある今、火花のような勢いはだんだんに冷め、それと入れ替わるように、未来への不安がもたげてくる。
今の自分は、大海原に投げ出された小舟のようなものだ。
たった一つの”言い伝え”だけを頼りに、在るのか、無いのか、分からないゴールを目指して、必死に小さなオールを漕いでいる。
自由を得る為に、家も、友人も、持ち物も、すべてをかなぐり捨ててきた。
あるのはこの身と心だけ。
頼れるものなど、何一つない。
ここから先は、全てを自分の手で掴み取らねばならない。
住む家も、着る物も、食べ物も、今まで当たり前のように身の回りに存在したもの、全てだ。
これから先、本当に自力で生きていけるのだろうか。
“君はまだ無力な子供"――と港の出国審査官は彼のことをそう呼んだ。
その言葉が、今さらのように身に染みる。
だが、彼はぐっと頭をもたげ、自分に言い聞かせる。
これは人生の試金石だ。
自分らしく生きる為の――。
自分が何ものかを知り、心のままに生きていくには、あの父から独立するより他なかった。
自分の意志を貫き、自由を得ようとすれば、それ相応の代償を支払わねばならないのは当然だ。
それを克服してこその自立であり、自由ではないか。
これからいろんな出来事があるだろう。
もっと辛く、哀しい出来事も。
だからといって、どうにも出来ずに逃げ帰れば、それこそ人生の敗北だ。
ああ、やっぱり父の言う通りだったと、この先も奴隷みたいに項垂れて生きていくしかない。
彼は臆病風を追い払うように深く息をつくと、再び窓の向こうを見つめた。
まだ目的地の明かりは見えず、果てしない闇が広がるばかりだ。
だが、どこか優しく感じるのは何故だろう。
今は独りだが、何かが自分の航路を祝福してくれているようにも感じる。
これは人生の片道切符。
何があろうと、決して負けはしない。
必ず目的を果たして、自分だけの価値ある何かを打ち立ててみせる。
小説『三番街でピアノが鳴ったら』の下書き(1997年)

