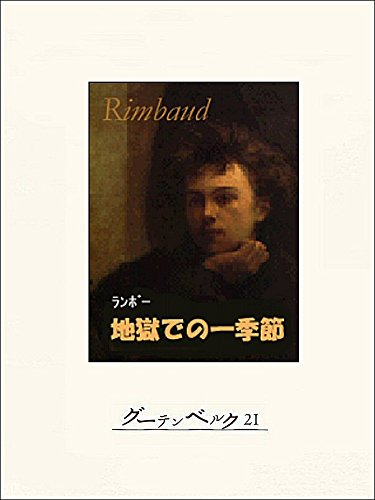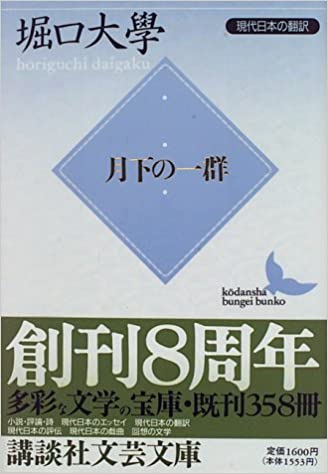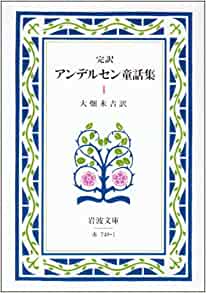寺山修司の『人生処方詩集』に掲載されていたフランスの詩とイギリスの名句の中から、お気に入りの作品を紹介しています。
フランス 恋の詩
夜のパリ : ジャック・プレヴェール
三本のマッチ 一本ずつ擦る
夜の中で
はじめのは きみの顔を隈なく見るため
つぎのは きみの目を見るため
最後のは きみのくちびるを見るため
残りのくらやみは 今のすべてを想い出すため
きみを抱きしめながら
- ジャック・プレヴェール -
プレヴェールの恋の詩は、いずれもロマンティックで、情景が目に浮かぶよう。
一瞬で燃えつきるマッチの中に恋する人の面影を歌う。素晴らしい抒情性です。
恋する二人 : ジャック・プレヴェール
恋する二人は立ったまま抱き合い
夜の戸口によりかかる行き来のひとがゆびさすけれど
恋する二人には だれもみえない二人の影ばかり やみにふるえて
行き来のひとの怒りをまねく怒りやさげすみ
わらいやそねみ
恋する二人には だれもみえない夜より遠く 昼より高く
二人はいまや
目くるめく初恋の光の中-ジャック・プレヴェール -
階段を半分降りたところ : A・A・ミルン
階段を半分降りたところに
あたしの坐る場所があるのこれとそっくり同じ階段は
どこにだってないいちばん下でもないし
てっぺんでもないだからあたしはいつでも
そこで止まって坐っているの- A・A・ミルン -
ミルンの詩もいいけれど、『人生処方詩集』の中にこの詩をピックアップした寺山修司のセンスも好き。
「一番下でもないし、天辺でもない」というのが、女性の戸惑いや、ちょっと疲れた暮らしぶりを感じさせます。
庭 : ジャック・プレヴェール
限りなく年を重ねても
言いつくせないだろう
あの永遠のわずかな一瞬
きみが私に口づけし
私がきみに口づけをした時のことを冬の光をあびた朝
パリのモンスリ公園で
パリで
星の地球の上で- ジャック・プレヴェール -
ジャック・プレヴェールの数ある詩の中でも、特にロマンティックな恋の詩。
くるくると世界が回るようなカメラ視点がいい。

五月の唄 : ジャック・プレヴェール
ロバと王様とわたし
あしたはみんな死ぬ
ロバは飢えて
王様は退屈でわたしは恋で
白墨の指が 毎日の石盤に
みんなの名を書く
ポプラ並木の風が
みんなを名づける
ロバ 王様 人間と太陽は黒いぼろきれ
みんなの名前はもう消えた
牧場の冷たい水 砂時計の砂
バラ色のバラの木のバラの花
小学生の道草の道ロバと王様とわたし
あしたはみんな死ぬロバは飢えて
王様は退屈で
わたしは恋で時は五月
いのちはサクランボ
死はその核(たね)恋は
サクランボの親の木

NEVERMORE : ポール・ヴェルレーヌ
彼女と私は二人きりで、 夢見ながら歩いていた、
風に髪と思いをなびかせて。急に、私の方に、 感動的な眼差しを向け、
「あなたの最も美しかった日はいつのこと?」 と、
彼女の息づく黄金の声。その甘く、響きのいい声は、天使の爽やかな音色。
つつましい微笑みがそれに答え、
私は、敬虔に、その白い手に口づけをした。ああ、 初花の何とよい香りがすることだろう!
心を魅するささやきのこもった、
愛する人の唇から出る、
何という最初の「諾(ウイ)」- ポール・ヴェルレーヌ -
一番惹かれたのは、“ああ、 初花の何とよい香りがすることだろう! ~ 何という最初の「諾(ウイ)」” の一節です。
ヴェルレーヌの原詩が……というよりは、邦訳が好きなのですが。
「Oui(ウイ)」に承諾の『諾』という漢字を用いるセンスが素晴らしい。
「あなたの最も美しかった日はいつのこと?」 という問いかけも綺麗ですね。
私もヴェルレーヌの詩はいくつか読みましたが、情景も、言葉のセンスも、この詩が一番好きです。
あなたの愛を口に出そうとしてはならぬ : ウィリアム・ブレイク
あなたの愛を口に出そうとしてはならぬ
愛は 口では言い表し得ないもの
優しい風は 目には見えず
こっそりと静かに吹くもの
- ウィリアム・ブレイク -
寺山修司の言葉に「現代人に欠けているのは「話し合い」より「黙りあい」」という言葉がありますが、好きな気持ちも、ぺらぺら口に出して表すのではなく、心と心で感じたいものです。
人魚姫 : アンデルセン
「ではわたしは、死んだら海の泡になって漂って、もう波の音楽も聞かれず、きれいな花や、赤いお日さまを見ることもできないのですね。どうかして、不死の魂を授かることはできないものでしょうか?」
―― 「だめ、だめ!」と、おばあさまは言いました。
「けれど、もし誰か人間が、お前を可愛がって、お父さんお母さんよりもお前の方を愛しく思い、心の底からお前を愛して、神父様に来てもらって、自分の右手をお前の手の中に置きながら、この世でもあの世へ行っても、いつまでも心の変わらない約束をしたなら、その時は、その人の魂がお前の身体の中へ乗り移って、お前も人間の幸福を分けてもらえるようになるんだそうだよ。その人は、お前に魂を分けても、自分の魂は、やっぱり元通りにもっているんだからね」
「これはきっとあの方が、海の上を船で通っていらっしゃるのだわ。お父さまお母さまより大好きな、あの王子さまが。ああ、私のひとすじに思っているあの方の手に、私の一生の幸福をおまかせすることができたなら!
あの方と、不死の魂とが、私のものになるなら、私はどんなことだってやってみるわ!」ここに一つの伝説――童話がある
深い塩からい海底に住むすべての貝は
じぶんの真珠を作り出した時には
死ななければならぬのだとおお愛よ!
私の胸に与えられたお前は
命を代償として真珠となるのだ- ハンス・クリスチャン・アンデルセン -
誰もが知っている名作童話も、改めてアンデルセンの著で読み返せば、また違った感慨があります。多くの人は、子供向けに編集された、いわば二次創作の絵本で終わってしまうケースが大半だと思うので。
「あの方と、不死の魂とが、私のものになるなら、私はどんなことだってやってみるわ!」
絵本の人魚姫と、アンデルセンの人魚姫では、造形がかなり違います。
また、絵本では、魔法使いのおばあさんは悪人に描かれますが、アンデルセンの原著では、悪い魔法使いというよりは、『知恵をもった老女』というイメージがあります。魔法は、知恵の延長として。
ミラボー橋 : ギョーム・アポリネール
ミラボー橋の下をセーヌ河が流れ
われらの恋が流れるわたしは思い出す
悩みのあとには楽しみが来ると日も暮れよ 鐘も鳴れ
月日は流れ わたしは残る手と手をつなぎ 顔と顔を向け合おう
こうしていると 二人の腕の橋の下を
疲れたまなざしの 無窮の時が流れる日も暮れよ 鐘も鳴れ
月日は流れ わたしは残る流れる水のように 恋もまた死んでゆく
恋もまた死んでゆく 命ばかりが長く
希望ばかりが大きい日も暮れよ 鐘も鳴れ
月日は流れ わたしは残る日が去り 月がゆき
過ぎた時も 昔の恋も
二度とまた帰って来ないミラボー橋の下をセーヌ河が流れる
日も暮れよ 鐘も鳴れ
月日は流れ わたしは残る- ギョーム・アポリネール -
マリー・ローランサンとの恋に破れたアポリネールが綴ったとされる有名な詩。
河の流れは悠久だが、恋は一瞬。
セーヌ河でなくても、ヨーロッパの大河を目にすると、必ず思い出す詩です。
ちょっと変形した女 : ポール・エリュアール
悲しみよ さようなら
悲しみよ こんにちは天井のすじの中にも
お前は刻み込まれているわたしの愛する目の中にも
お前は刻み込まれているお前はみじめさとはどこかちがう
なぜなら
どんなに貧しい子でも
ほほ笑みながら お前を見せてくれる悲しみよ こんにちは
ただ燃えるだけの肉体の愛
その愛のつよさだけどからだのないお化けのように
希望に裏切られているお前の悲しみ美しい顔よ
『悲しみよ こんにちは』のフレーズは、フランスの女流作家、サガンの有名なデビュー作のタイトルで知られています。
あまりにもこのタイトルが有名である為、この詩のタイトルも「悲しみよ こんにちは」というイメージがありますが、邦訳は『ちょっと変形した女』です。
言葉としては、後者の方が味わいがありますね。
愛は旅路を見出す : トマス・パーシー
山を越え
海を越えて
愛は
その旅路を見出す
- トマス・パーシー -
愛とは息の長いものです。ぱっと燃えて、ぱっと燃えつきるものではない。
嫌なこともあれば、逃げ出したくなることもある。
旅路というのは、本当にその通りです。
ソネ 第八番 : ルイーズ・ラベ
私は生き、私は死に、
私は燃え、私は溺れる私は冷たさに耐えながらも、極度に熱い
人生は私にやさしいかと思えば 厳しすぎもする私は歓喜のまじり合った 深い物憂さを感じている
笑うかと思えば、私は涙し、
快楽に身を委ねながらも、 辛い苦しみに耐え、
私の幸福が遠く去るかと思えば、 永遠に続く 突然、
私は疲れ果てるかと思えば、 緑に萌えるこのように「愛」は変わりやすく、私をひきずってゆく。
そして苦しみがつのるかと思えば、 知らないうちに、
その辛さから逃れ出ているのだ
だから私が この歓喜を確かなものと思えば
私の望んだ至福から
「愛」は私をふたたびはじめの不幸へと
突き落としてしまう……愛は私を深く傷つけたため
時間が経っても 今もなお その跡は癒えない嘆きの歌をうたい それでもなお私は
過ぎた不幸を 新たにするほかない- ルイーズ・ラベ -
『人生は私にやさしいかと思えば 厳しすぎもする』という一文が気に入って、クリップ。
似たようなフレーズは谷川俊太郎の詩『世界が私を愛してくれるので』にもあって、それぞれに自分の言葉で人生を表現しているのが感慨深い。

「恋する女」の存在の不安は、たえず相矛盾する極から極へ移ることから生じる。
愛は生から死へ、歓喜から涙へ、苦しみから安らぎへ、至福から絶望へと絶えず詩人を揺り動かし、片時も休むことがない。
愛は、もっとも信じていることを疑わせる力を持つとすれば、また他方、ラ・ロシェフーコー風にもじって言えば、もっとも利口な人間を愚かにし、もっとも愚かな人間を利口にするという狂気の状態に人を置く。
それを時々刻々に己の内部に体験することは、まさにこの世に何一つ確かなものはないと人に思わせるに十分であろう。
ある意味、利口な人間というのは、心が死んでいるのです。
心が生きている限り、また、人と関わる限り、絶えず不安に苛まれるものなので。
愛と死は、愛が昂まるにつれて不可分となる。
死と愛は表裏の関係にある。
エロスは死と近接する度合いにおいていっそう至高を目指すものである。その愛の中で、二人の一体感はあまりにも強く、もはや二人はお互いを別々のものと感じることができない。
それは一つのもの、一つの存在となる。
固有のものを失ってともに一つに融け合ってしまう。
中世の愛の神話「トリスタンとイズー」と同じく、一つの存在になる以外にない。というのも、愛とは燃えつくすまでやまない自転的なエネルギーそのものであり、それは全てをこえてしまう。生涯が多ければ、尚いっそうのことである。
本来、「恍惚(extase)」とは接頭語「ex」が示しているように、「自分」の外へ出ることによって味わう感覚のよろこびである。すすんで「自己」を失おうとする働きである。
それは極限において「自己」のみならず「生」の外に出て行こうとする運動性をもち、しかもそれを「幸せ」と思う情念によって支えられている。- 「四季 ~フランス詩集より~」 解説の抜粋
恋 : ジョン・メイスフィールド
恋は
人間の心を燃やし尽くし恋は
その意志に火をはなつ恋は人を
ぬかるみに陥らせ恋は運命の矢に
苦い毒をぬる- ジョン・メイスフィールド-
よく「恋愛なんてバカみたい」と見下す人もありますが、恋というのは、感性の問題であって、本人の魅力うんぬんの問題ではありません。
恋人がいようが、いよまいが、恋愛経験が豊富であろうが、なかろうが、人が人に恋する心情を理解できるか否かが重要なんですね。
詩で味わうことも、十分、意義があると思います。
この詩は、恋の痛み、苦しみ、情熱、全てを物語っていると思います。
イギリスの名句
思想のない言葉は天には届かない : シェイクスピア
言葉はどんどん出てくるが
思想はなかなか出てこない
思想のない言葉は
天には届かない
-ウィリアム・シェクスピア-
人生を楽しめる時 : ジョン・キーツ
もっと人生を
ほんとうに楽しめる時が
いつかは 訪れるだろう──
その時を
あなたは心待ちにしなさい
-ジョン・キーツ-
薔薇の蕾 : ロバート・ヘリック
あなたが摘める間に
薔薇の蕾をを摘みなさい時は待っていてはくれない
今日 微笑のあるこの薔薇は
明日にはもう 散ってしまうのだから- ロバート・ヘリック -
- なみだは にんげんのつくることのできる 一番 小さな海です ~寺山修司 海の詩
- 詩心がなければ世界は灰色 『葬式に行くカタツムリの唄』ジャック・プレヴェール
恋する気持ちや少女の切ない心情を美しい言葉で表した詩集より。
言葉の色彩感が素晴らしいプレヴェールの名作です。
【書籍の案内】 珠玉のフランス詩集
フランス 四季と愛の詩
これほど美しい詩集もまたとない。
四季の叙情と愛を美しいフルカラーの写真と合わせて綴る、まさに溜め息の出る一冊。
フランスの原詩と詩人の生涯、文学についての詳しい解説もあり、「感じたい」「学びたい」方におすすめの本です。
参考: 饗庭孝男『フランス 四季と愛の詩』 ~詩と写真で感じる大人の絵本
この本にはランボーやボードレール、プレヴェールといった、誰もが知る詩人と名詩がピックアップされており、選詩そのものに真新しいものはないのだけども、なんせ饗庭さんの感性と解説が素晴らしいでしょう。
「ああ、あれ、どっかの詩集で読んだわー」なんて言わずに、この本を通じて二度目の出会いを楽しんで欲しい。
プレヴェール詩集
ジャック・プレヴェールの本は、日本で長い間、刊行されてなかったが、2017年に岩波文庫より再版。
特に美しいのが、「詩心がなければ世界は灰色 『葬式に行くカタツムリの唄』です。
地獄での一季節
数あるランボーの書籍の中でも、特に情熱的で、ランボーの激しい詩情が感じられる名作。
小林秀雄・訳(岩波文庫)に挫折した人におすすめ。
参考: アルトゥール・ランボーの詩集 『地獄での一季節(篠沢秀夫・訳)』より
月下の一群
翻訳詩といえば堀口大學の『月下の一群』に尽きる。
教科書でもお馴染みのあの名訳が存分に楽しめる一冊。
完訳アンデルセン童話集
「童話」ではあるが、様々な示唆と深い哲学性、宗教性に富んだ内容は、大人でも胸を打つものがある。
大人になってから改めて読むと、ほんと号泣しますよ。
第一集には上記で紹介した「人魚姫」が収録。
子供向けに編集されたものと異なり、かなりキリスト教的な色合いが強いです。
初稿 1998年秋