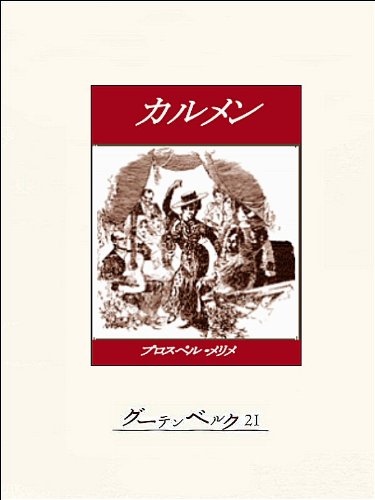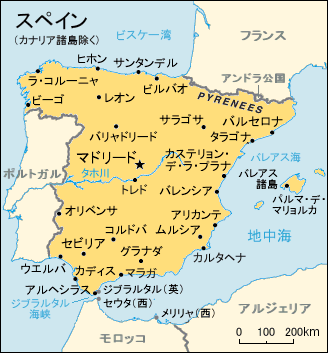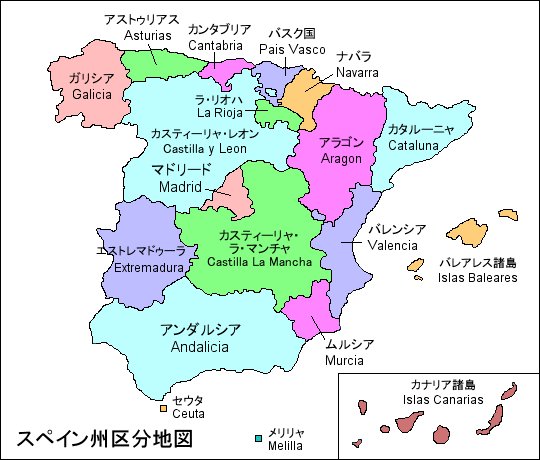メリメの小説『カルメン』の見どころ
原作と映画・オペラの違い
カルメン(Carmen)と言えば、「炎の女」「自由奔放」「口にくわえた薔薇一輪」「フラメンコ」など、どんな女性か、すぐに想像がつくと思います。
しかし、その多くは、映画やオペラのイメージからもたらされたもので、プロスペル・メリメの原作『カルメン』は、スクリーンの中の美女とちょっと違っています。
もっと蓮っ葉で、情け知らずとでも言うのでしょうか。(蓮っ葉とは、言動が浮薄なこと。特に,女性の態度やおこないに品がないこと。また,そのさま。そのような女性をもいう。「―な言い方」 by 大辞林4.0)
訳文の口調が「あたし」「おまえさん」「~してやるよ」「~じゃないのかい」みたいなので余計でそう感じるのかもしれませんが、漫画や映画で描かれるカルメンほど若々しくもないし、どちらかといえば、どんと肝の据わった、○○組の姐さんみたいなタイプです。
異性関係も、生粋の男好きというよりは、打算で色気を振りまくタイプ。相手に利用価値がある間は、恋人みたいに優しく振る舞いますが、ひとたび気持ちが冷めたら、見向きもしません。まして、ドン・ホセのように生真面目な男に扱えるはずもなく、最後は悲劇で終わります。
しかし、原作は、びっくりするほど短くて、カルメンとドン・ホセが主人公ではありません。(主人公には違いないが、劇中の回想として語られる)
主役は、ローマ時代の幻の古戦場を求めて、スペイン中を旅して回る考古学者であり、カルメンの恋物語は、刑務所で死刑執行を待つ盗賊ドン・ホセの回想として語られます。
テーマも一貫して「言語と文化」であり、カルメンはボヘミア文化を象徴するアイコンみたいな存在です。
わけても鍵となるのが、二人の話す「バスク語」です。
ドン・ホセは、カルメンの美貌以上に、カルメンの話すバスク語に心を惹かれます。
難解で知られるバスク語は、ドン・ホセの故郷の言葉だからです。
映画やオペラでは、バスク語のことはほとんど話題にならないので、初めて原作を読んだ人は、かえって新鮮に感じると思います。
世界的に有名な物語なので、取り立てて小説を読む必要もない――と感じる人もあるかもしれませんが、原作では、スペインの言語や文化風習、人間性などに宇ウェイトが置かれ、スペイン文化の入門編として楽しめます。
また、「大長編」のイメージがありますが、ページ数も100ページほどしかなく(Kindle版)、1時間ぐらいで、サクっと読めますので、興味のある方は、ぜひお手にとってみて下さい。
グーテンベルク版・江口清氏の訳文も秀逸です。
こんな話だったのか……! と驚くこと請け合いです
Kindle Unlimited対象商品です。(外れる時もある)
Kindle Unlimitedの案内を見る(Amazon公式)
映画とオペラで見る『カルメン』
『カルメン』に関しては、良質な映画やオペラ、舞台劇がたくさん制作されています。
未読の方、文章でイメージするのが苦手な方は、まずはビジュアルで世界観を把握しましょう。
こちらは2003年に制作されたスペイン語のドラマです。
動画編集でナレーションが入りますが、全体の流れをざっと掴むのにおすすめです。ナレーションが不要な方は音声をミュートして下さい。
こちらは有名なカルメンとドン・ホセの出会いです。赤いアカシアの花を投げるシーンも素敵。(薔薇ではない)
2003年度のドラマは、カルメンも現代的で、妖艶というよりは可愛いタイプですが、原作のカルメンはもっとふてぶてしい、姉御タイプです。
こちらはメトロポリタン歌劇場によるオペラ『カルメン』。女たちが働くセビーリャの煙草工場で、カルメンが『ハバネラ(恋は野の鳥)』を歌います。
原作でも細かな描写がありますが、ビジュアルだと、より分かりやすいです。
低賃金で働く女たちのムンムンとした雰囲気が伝わってきますね。
カルメンのイメージも、2003年のドラマより、原作に近いです。
オペラに興味のある方は、「OPERA CARMEN」で検索して下さい。いくつかの動画が公式チャンネルから全編アップされています。
こちらは有名な『闘牛士の歌』。日本のCMでもよく使われるので、一度は耳にした方も少なくないのではないでしょうか。
オペラでは、闘牛士エスカミーリョが恋のライバルとして登場しますが、原作では、案外、あっさり事故死(?)します。
また、オペラでは、ドン・ホセの婚約者ミカエラが重要な役回りを演じますが、原作には存在しません。
小説『カルメン』の名言集
本作には、「コルドバ」「アンダルシア」「セヴィーリャ」など、日本人にもお馴染みの地名がたくさん出てきます。しかし、それが何所に在るのか、正確に知っている人も少なくないのではないでしょうか。事前に把握しておいた方が、彼らの放浪がより理解できるので、参考にどうぞ。
スペインの主要都市とスペイン州区分地図です。
考古学者と盗賊ドン・ホセの出会い
小説『カルメン』は、スペインの歴史や文化に詳しい考古学者の道中から始まります。
考古学者は、ローマのシーザーが共和国のそうそうたる連中を相手に決戦を交えたと伝えられる、「ムンダ」の古戦場の位置を探し求め、スペイン中を旅しています。
彼はコルドバで一人の案内人と二頭の馬を雇い、『シーザーの記録文書』を頼りに旅を続けますが、直射日光と喉の渇きに苦しめられ、峡谷の中のオアシスのような場所で休息を取ります。
そこには既に先客がいました。小銃を携えた、陰気で、頑丈な男です。
案内人は、一目見て、男の素姓を見抜きますが、考古学者は、彼と一緒に葉巻を楽しみます。
スペインでは葉巻のやり取りは、近東でパンと食塩とをわかち合うのと等しく、親密な関係を作り出すのだ。
その後、考古学者は、旅籠屋(パンタ)で再び男と再会し、宿の老婆とのやり取りから、男の名前が「ドン・ホセ」と知ります。
ドン・ホセはマンドリンを上手に弾き(考古学者いわく、スペインはどこに行ってもマンドリンがあるらしい)、感激した考古学者は彼の歌について尋ねます。
「もしわたしの聞き違いでなければ、あなたが今うたわれたのは、スペインの歌じゃありませんね。なんだか地方で聞いたことのあるソルシコス(このバスク地方のダンス歌謡曲)に似ている。文句は、バスク語(スペインの北東部、フランスとの国境地方のことば)ですね」
「そうです」とドン・ホセは暗い顔をして答えた。
やがて案内人は、その場をこっそり抜けだし、高額な報償金を目当てにドン・ホセを警察に突き出そうとしますが、考古学者はドン・ホセを逃がしてやります。「ドン・ホセ、君にしてあげたお礼のかわりに、わたしに約束してもらいたいことがあるんだ。それはね、だれも疑わないことと、復讐することを考えないことだ。さあ、この葉巻は道中でやってくれたまえ」と。
考古学者、カルメンに時計を盗まれる
その後、考古学者は再びコルドバに向かい、カダルキビール河の土手の川べりで、美しい女に出会います。考古学者は、彼女の「柔らかいことばつき」から、コルドバか、アンダルシアの方ですか? と訊ねますが、彼女はボヘミアの女(ロマのこと。チェコのボヘミア地方ではない)で、名前はカルメンシタと答えます。
カルメン嬢が生粋のボヘミア人であるかどうかは、はなはだ疑わしく思う。が少なくとも彼女は、今までわたしが会ったボヘミアの女よりも、はるかに美しかった。スペイン人の言によると、一人の女が美人であるためには、三十の条件を備えていなければならないそうだ。もっと言えば、女の三つの部分に、それぞれ適用できる、十個の形容詞をもって品評できなければいけないというのだ。
≪中略≫
わたしのボヘミアはしかし、それほど完成した美を誇るわけにはゆかなかった。肌は、まず完全になめらかだったが、その色は銅色にはなはだ近かった。目は斜視だし、すばらしい、切れあがった目だ。唇はいささか厚いが、いい形で、そのあいだに、皮をむいた巴旦杏(はたんきょう)の実のよりも白い歯並びをのぞかせていた。髪は、おそらく少々こわいが、まっ黒で、鳥の翼のように青びかりのする、つややかなたけながな髪である。
≪中略≫
それは、不思議な、野性的な美しさであり、ひと目で見た者をまず驚かすが、けっして忘れることのできない顔だちなのだ。とくに彼女の目は情欲的で、同時に残忍性をおびており、わたしはこのような人間の目つきを見たことがなかった。ボヘミア人の目は狼の目だ、というスペインのことわざがあるが、なかなか鋭い観察を示しているといえよう。
さらにカルメンは、占いの達人でもあります。本作にも、占いの場面がよく登場します。
占いと言っても、魔術や超能力の類いではなく、日本でも田舎のお婆さんがよくやる、民間伝承の亀甲占いみたいなものです。
二人きりになるとボヘミア女は、手箱の中から使い古したらしいカルタと、磁石と、ひからびたカメレオンと、そのほか彼女の術に必要なものを取り出した。そして、銀貨で左手の掌に十字をきれと、行った。かくて魔術ははじめられたのである。
ここでも、カルメンのルーツを思わせる、言葉の話題が登場します。
ジプシーの女は男の姿を見ても、べつに驚きも怒りもしなかった。それどころか、みずから進んで男に近寄り、驚くべき早口で、すぐにわたしの面前で使った不可解なことばで話しかけたのだ。彼女の話の中でしばしば使われる payllo なることばが、唯一のわたしにわかることばだった。このことばは、ボヘミア人が自分の種族以外の者を呼ぶときに使うのだということを、わたしは知っていたからだ。
上記のように、本作には、言語に関する話題が随所に盛り込まれています。
カルメンも、ドン・ホセも、スペインの男女ではなく、『バスク語の話者』として描かれているのが本作の特徴です。
考古学者は、女と話した後、自分の時計が無くなっていることに気がつきます。油断している隙に、すられたわけですね。現代の海外旅行でもよくある話です。
しかし、取り返すのは諦め、旅を続けます。
ドン・ホセの告白 : カルメンとの出会い
その後、数ヶ月、アンダルシアを彷徨した考古学者は、首都マドリッドに帰ろうとしますが、その為には、コルドバを通過しなければなりません。
しかし、ボヘミア女と時計の盗難で嫌な思いをしたこともあり、気が進みません。
それでも、コルドバに数日滞在する予定で、ドミニコ派の修道院に立ち寄ると、教父から、盗まれた時計と犯人が見つかったと報告を受けます。
犯人とは、ドン・ホセでした。彼は重犯罪者として牢獄に繋がれ、絞首刑を待つ身でした。
考古学者は、葉巻のこともあり、獄中のドン・ホセを訪ねます。
ドン・ホセは、首にかけていた小さな銀のメダルを考古学者に手渡すと、「旅籠屋の老婆に渡し、わたしが死んだとおっしゃっていただきたいのです。どうして死んだのか、それはおっしゃらないでください」と懇願します。
その続きで、カルメンとの恋物語が語られます。
*
ドン・ホセは、バスタンの谷間の、エリソンドに生まれました。バスク人で、古くからのキリスト教徒です。
アルマンサの騎兵連隊に入隊したドン・ホセは、セビーリャの煙草工場の警備を受け持つようになります。
当時私は、ほんのこどもでした。いつでも故郷のことばかり考えていたのです。青いスカートをつけて、編んだ髪を肩までたらしている娘よりほかには、きれいな女はいないと思っていたのです。それどころか、アンダルシアの女は、おそろしくさえあったのです。いつも人をからかい、けっして本気でものを言わない、そういうアンダルシアの女に慣れていなかったのでした。
で、私は、あいかわらず鎖に顔を押しつけていました。すると町の人々の「そら、ヒタニリャ(スペインに住むボヘミヤ女をこう呼ぶ)が来た」と言う声がしました。私は目を上げました。あの女を見たのです。 ≪中略≫ 女は赤いペチコートをはいていましたが、短いので、穴のあいている絹の靴下がむきだしでした。赤いモロッコ皮のかわいらしい靴は、燃えるようなまっかなリボンで結んでありました。彼女は肩を見せるために、ショールをひろげて見せ、アカシアの花を一輪くわえていました。そしてコルドバの牧場の若い牝馬のようにお、腰をふりふりやって来るのです。
私の故郷ででもあろうものなら、このような恰好をした女を見たものは、十字を切るところですが、セビーリャの町では、みんながなんとか言って、みだらな挨拶を浴びせるのです。彼女はその一人一人に、拳にを腰に当てて、まったくボヘミア女の名にそむかぬずうずうしさをもって、流し目を送りながら答えるのです。
私の故郷ででもあろうものなら、このような恰好をした女を見たものは、十字を切るところですが、セビーリャの町では、みんながなんとか言って、みだらな挨拶を浴びせるのです。彼女はその一人一人に、拳を腰に当てて、まったくボヘミア女の名にそむかぬずうずうしさをもって、流し目を送りながら答えるのです。ひと目見て、私は彼女がいやになりました。私は、やりかけていた仕事にまた取りかかったのです。すると彼女は、女と猫とは人が呼ぶときには来なくて、呼ばないときにやってくると言いますが、そのたとえのごとく、私の前に足を止め、ことばをかけたのです。彼女はアンダルシアふうに、言いました。
女もまた、ドン・ホセに目を留めると、口にくわえていたアカシアの花を投げつけます(薔薇ではない)
ドン・ホセはアカシアの花を拾い上げると、たいせつに上着の中にしまい込みます。ドン・ホセいわく、「まず、『どじ』を踏んだというわけです」
その後、カルメンは、煙草工場の女工と喧嘩になり、相手の顔を小刀で切りつけます。
原作では、「サン・タンドレの十字を描く」と表現されています。
サン・タンドレ(Sant Andreu)は、十二使徒の一人、聖アンデレ(Wikiで見る)のことです。聖アンデレは、X字型の十字架で処刑されたことから、下図のような「聖アンデレ十字(Wikiで見る)」が彼のシンボルとなっています。
ちなみに、「イクリニャ」と呼ばれるバスク地方の国旗は「バスク十字」と呼ばれ、聖アンデレ十字によく似ています。
興味のある方は、バスク地方(Wiki)を参照して下さい。
バスク語を話す女 ~恋の始まり
カルメンは逮捕され、ドン・ホセと二人の竜騎兵が連行しますが、「蛇小路」にさしかかると、カルメンは色仕掛けで「あたしを逃してちょうだいよ」と哀願します。
ドン・ホセは、「ここで冗談を言うことは許されんぞ」と反駁しますが、、、
われわれバスク族の者は、特別のアクセントを持っていますので、容易にスペイン人と区別できます。ところがその反対に bai Jaona (「はい、そうです」の意)というのを覚えることのできるスペイン人は、一人だってありゃしません。ですからカルメンは、私がバスクの男だと、すぐ察しました。
ご承知でもありましょうが、ボヘミア人っていうのは、どこといって故国があるわけではなく、どこの国のことばでも話します。たいていのやつは、ポルトガル、フランス、バスク地方、肩ローニャ、その他の所々のほうぼうが、彼らの故国同然なのです。マウル人(北アフリカの現住民の一種族)やイギリス人とさえも、話がつうじるのです。
カルメンはかなりよくバスク語を知っていました。とつぜん私に向かって、こう言うのです。
「ラグーナ、エネ・ピオツアレーナ、あら、あなた、あたしと同じ故郷ね?」
私どもの国のことばは、旦那さま、そりゃ美しいことばなんです。ですから他国にいてそれを聞くと、思わず気持ちがわくわくしてくるのです。
ドン・ホセの心を掴んだのは、カルメンの色香ではなく、『バスク語(Wikiで見る)』という共通の文化でした。
日本でも、故郷の方言を耳にすると、妙に親しみを感じるように、ドン・ホセも、「バスク語を話す同郷の女」というだけで、心を鷲掴みにされます。
バスク地方のグルメや文化については、旅行会社のサイトが参考になります。 スペイン、フランス、バスク地方旅行 美食と独特の文化と旅する喜び(ユーラシア旅行社)
カルメンに魅せられたドン・ホセは、カルメンに突き倒された振りをして、彼女を逃がしてやります。
これが原因で、ドン・ホセは位階を下げられ、一ヶ月間、営倉へ送られます。出世の望みも断たれて、これが転落の始まりでした。
夢のような一夜
しかし、ドン・ホセはカルメンのことが忘れられません。営倉でも、彼女の面影を胸に抱き、思いを募らせます。
ある日、看守がやって来て、「おまえの従妹から差し入れだ」と、アルカラのパン(アルカラという町は、セビーリャから8キロほど離れたところにあり、非常にうまい小型のパンができる)を渡してくれます。しかし、ドン・ホセには従妹などいません。しかも、パンの中には、イギリス製の”やすり”と、2ピヤストルの金貨が一枚入っていました。ドン・ホセはすぐにカルメンの差し金と気付きます。
ボヘミア人にとっては、自由こそすべてで、やつらは一日の牢獄生活からのがれるためには、一つの町も焼き払いかねないのです。それにあの女は悪達者な女ですから、こんなパンを差し入れて、看守人を愚弄したわけなのです。
しかし、ドン・ホセは脱獄はせず、きちんと刑期を終えて出所します。
今度は、大佐の家の門の歩哨として任務に就きます。
すると、またそこに美しく着飾ったカルメンがやって来ます。
彼女はこのとき、金やリボンでごてごてに飾られた聖遺物箱のように、あくどく飾りたてていました。金モールで飾った着物、同じく金モールの飾りのある青い靴、そして体中に、花や飾り紐をつけていました。彼女はバスク族特有のタンバリンを、手に持っていました。 ≪中略≫ 私はカスタネットとタンバリンの音、笑い声と喝采とを聞いたのです。ときには、タンバリンを持ったまま躍り上がる拍子に、彼女の顔が見えることもありました。
このあたりが、「フラメンコ」「炎の女」として描かれるんでしょうね。
本作に登場する「ボヘミア人」「ボヘミア女」とは、チェコのボヘミア地方ではなく、いわゆるロマ(ジプシー)を指します。同時に、「ボヘミアン」=「流れ者」「自由奔放な人々」の意味もあり、カルメンはロマと流れ者の象徴です。
スペインのジプシーの踊りは、こんな感じ。
タンバリンを使ったジプシーの踊り。
大佐のパーティーが終わると、カルメンは帰り際にドン・ホセに声をかけ、「トリアナのリリヤス・バスチアのところへ行ってごらんなさいよ」と促します。
そこは、リリヤス・バスチアは、モール人のように色の黒いボヘミア人で、老人が営む天ぷら屋で働いています。
ドン・ホセはそこでカルメンに再会すると、「牢屋に入っていた時にもらった贈り物の礼を言わなければならない」と申し出、カルメンと連れ立って、セビーリャの町に行きます。
そこで、果物や、ぶどう酒、お菓子を、しこたま買い込むと、「蛇小路」(ドン・ホセがカルメンを逃がした場所)の古びた家を訪れ、二人きりになります。
おまえはあたいのロム、あたいはおまえのロミ(ロムは夫。ロミは妻)。
あたし、借りは払うわよ。これが、カレ(直訳すれば「黒」を意味するが、ボヘミア人はこのことばを使って、互いに呼び合う)のあいだのおきてだもの!」
カルメンはドン・ホセの首に抱きつき、情熱的な一夜を過ごします。
誰のものにもなりたくない
ところが、カルメンはあっさりしたものでした。「おまえさんはきれいな男だし、あたしはおまえさんが好きになったの。だけど、これでお別れさ。さようなら」と別れを切り出します。
ドン・ホセが今度はいつ会えるのかと尋ねると、
ねえ、おまえさん、あたしは少し、おまえさんが好きになったようなんだけど? だが長つづきしないさ。犬と狼とじゃ、長いこと所帯は持てませんからね。おまえさんは悪魔に出会ったんだからね。そうだよ。悪魔なんだよ。悪魔は、いつも黒い身体をしているとは限らないものね。 ≪中略≫ こんりんざい、カルメンシタのことを考えちゃいけないよ。でないとカルメンシタはおまえさんに、木の足のやもめ婆さん(絞首台で最近縛り首にあった男やもめから、この場合、たんに絞首台を意味している)をめとらせてしまうよ
カルメンは冷たく言い放ち、ドン・ホセに背を向けて、遠くに行ってしまいます。
ドン・ホセ、密輸に手を出す
それから数週間後、再び、ドン・ホセは歩哨として町の門戸に立ちます。
夜になると、再びカルメンがやって来て、ドン・ホセを誘惑します。
カルメンに抗えないドン・ホセは、カルメンの願いを聞き入れ、カルメンの仲間五人を通してやります。彼らは密輸仲間で、イギリス製の商品をどっさり背負っていました。
その後、ドン・ホセはカルメンに言われるがままに、密輸業者の仲間入りをし、悪事に手を染めるようになります。
カルメンの情夫で、親方でもある『片目のガルシア』が負傷した仲間を撃ち殺すこともありました。
ドン・ホセが「おまえは、悪魔だ」とカルメンを詰っても、「そうよ」とカルメンはいっこうに平気です。
それでも、ドン・ホセはカルメンを思い切ることができず、彼女の気を引くために、盗賊になり下がります。
しかし、カルメンは、ドン・ホセの気持ちを踏みにじるようなことばかり。
激しく言い争った時も、カルメンはドン・ホセに抗います。
「ほんとを言うとね、はっきりあたしのロムになってからのおまえさんは、おまえさんがあたしのミンチョーロ(恋人。可愛い人)だったときより好きになれないのさ。あたしはいじめられるのもきらいだが、命令ずくで言われるのはことにきらいだよ。あたしの願いっていうのは、だれからも文句を言われずに、自分の好きなことができるってことさ」
そのくせ、ドン・ホセが軍隊に追われて負傷した時は、今までどの女もその男に対して尽くさなかったほどの熟練と熱心さをもって、看病に当たります。
やがてドン・ホセは悪事から足を洗い、新天地アメリカでカルメンと生き直すことを真剣に考えるようになります。
国力においても、工業化の進んだイギリスの方が上で、高級品も手に入りやすかったのでしょう。昔も今も、欧州はスリや密輸が多いですけど、一度やったら、やめられないんだと思います。
誰のものにもなりたくない ~カルメンの最後
度重なるトラブルの後、ドン・ホセは改めてカルメンに言います。
「おれは何もかも水に流すつもりだ。何も言いたくないんだ。ただ、このことだけを言ってはくれないか。それはな、おれと一緒にアメリカへ言って、静かな生活にはいるってことだ」
しかし、カルメンの返事はいつもと同じ、「いやだよ、あたしはアメリカへ行きたかないよ。ここで結構さ」。
でも、今度はドン・ホセも引き下がりません。
「もうおれは、おまえの男を一人一人殺すのに、あきあきしたよ。今度は、おまえを殺す番だ」
彼女は、あの野獣のような目で私をじっと見ながら、言いました。
「あたしはね、いつかおまえさんがあたしを殺すだろうって、いつも思っていたよ。。最初おまえに会ったときに、うちの入口で坊さんに行き会ったのさ。それから今晩だって、コルドバを出るとき、おまえさんは気がつかなかったかい? 一匹の兎が、おまえさんの馬の足のあいだをすり抜けて、道を横切ったんだよ。ちゃんと、占いに出てるのさ」
そして、もう一度、二人は寂しい峡谷に差し掛かると、同じ問答を繰り返します。
「ホセ、おまえさんはあたしに、できない相談をもちかけているんだよ。あたしはもう、おまえさんなんかにほれちゃいないんだからね。おまえさんのほうでは、まだあたしにほれている。だからあたしを殺そうっていうんだろう。あたしは、おまえさんに嘘をつこうと思えば、いくらでもできるだろうよ。だがね、もうそんな手数をかけるのはいやになってしまった。二人のあいだはもうすっかりおしまいになったのさ。おまええさんはあたしのロムなんだから、おまえさんのロミを殺す権利は確かにあるよ。だけどカルメンは、どこまで行っても自由なカルメンですからね。カリに生まれて、カリで死にますからね」
憤怒に私はわれを忘れ、短刀を抜きました。私は、彼女が怖れをなして、許しをこえばいいがと願ったのです。ところがこの女は悪魔でした。私は叫びました。
「さあ、これが最後だ! おれと一緒に生きてゆこうとは思わんか?」
「いや、いや、いやだ!」と彼女は足を踏みならして叫びました。そうして私からもらった指輪を指から抜き取ると、草むらの中へ投げだしました。
この後は、皆さんが知っている通りです。
ホセは言います。「みんなカレ(黒い人)たちが悪いんです。あの女をあんなふうに育てあげたっていうのは」
作者による後記: スペインとボヘミア人
本作の後記≪第四章≫は、考古学者――というよりは、メリメの解説で締めくくられています。
ここで改めてボヘミア人の特徴が語られ、
ボヘミア人の肉体的特徴は、百聞一見にしかずで、一度見ておけば、千人の中からこの種族に属する人間を、わけなく見いだすことができる。顔つきと表情、これがとくに、その国に住んでいる異人種と彼らを区別するものである。肌の色はひどく陽に焼けていて、彼らが共に生活している人々の皮膚の色よりも、はるかに黒いのが特徴である。ここから彼らがよく自分たちを言うときに使う「黒い人」という意味の、カレという名が出てくるのだ。
あきらかに斜視である彼らの目は、まっ黒で、目尻が切れていて、濃い長い睫でおおわれている。その目つきは、野獣の目というよりほかはない。そこには、大胆と臆病さが同時に現われている。
≪中略≫
ドイツでは、しばしば非常に美しいボヘミア女を見る。が、スペインのボヘミア女の中には、美人はごくまれである。それでも若いうちは、顔はまずくとも、まだ見られるが、一度母親になってしまうと、もう見られるもんじゃない。男女とも、その不潔さは想像外であって、ボヘミア人のおかみさんの髪を見たことのない人には、非常にこわくて、脂と埃だらけの馬の毛を想像しても、その汚さの観念を作りあげることはむずかしいだろう。
等々、かなり突っ込んだ記述がなされています。
結局、この小説は、何が言いたいかといえば、カルメンとドン・ホセの悲恋よりも、バスク語やボヘミア人といった文化の紹介にあり、カルメンは、それを象徴するキャラクターに過ぎません。それでも十分に魅力的ですが、小説全体を見れば、かなり違和感を覚えるのではないかと思います。
たとえば、映画『風と共に去りぬ』を見た人が、原作を読めば、「あ~、映画の通りだ」と納得するけども、『カルメン』は、「それが言いたかったんかい!!」と拍子抜けするようなところがある、という意味です。
だからといって、決して駄本ではなく、カルメンとドン・ホセの恋物語だけを抜き出しても不朽の名作に違いありません。
スペイン文化に興味のある人、旅行で訪れた人、スペイン語の専門教育を受けた人なら、「これ、分かる!」と歓喜するような描写もたくさんありますので、教養の一つとしてお読みになることをおすすめします。ほんと、100ページほどなので、すぐ読めます。あえて言うなら、カルメンの恋物語が始まるまでが、ちょい長い
訳本としては、新潮文庫の『カルメン』堀口大学・訳、岩波文庫の『カルメン』杉 捷夫・訳が、当方は、グーテンベルク版 江口清・訳をおすすめします。分かりやすい。
【参考】バスク語の参考サイト
日本語に似ていると言われるバスク語。ルーツや歴史について分かりやすく紹介しています。

スペインで話されている言語について紹介。その中でも、バスク語だけはまったく別系統のようです。

バスク語の文法について、詳しい解説があります。玄人向け。

【コラム】 一緒に居れば、恋も死ぬ ~カルメンは本当にドン・ホセを愛していたのか
カルメンは、本当にドン・ホセを愛していたのか、と問われたら、間違いなくイエスです。
ただ、他の女性のように、生涯添い遂げるような愛し方には興味がなく、愛を新鮮に保ちたいからこそ、世間並みな生き方を拒む。カルメンなりの愛し方であったように思われます。
男女が長い間、一緒に居れば、いずれマンネリ化し、上下関係や従属も生まれるもの。
ドン・ホセも、カルメンを夢中で追いかけている間は、世界最高の女と思い込んでいますが、カルメンが世間並みな主婦に収まれば、たちまち興味をなくし、今度は自分とは正反対な、真面目で、清純な女性に心を移すかもしれません。
カルメンのように、根っからのボヘミアンで、男の性情をよく知る女性には、ドン・ホセの熱情も、よくある情事の一つに過ぎず、夢など見ないのです。
カルメンは、いつかドン・ホセに殺されると予感していましたが、それが一番納得いく筋書きだからでしょう。
元々、帰る家もなく、家族もなく、うたかたみたいに生まれて消えていく人生です。
警察に捕まって、一生、牢獄に繋がれたり、衆目の中で縛り首にされることを思えば、愛する男の手にかかって、一番いい時に死ぬのが、カルメン的には幸福だったのかもしれません。
何にせよ、現実には有り得ない話だからこそ、映画に、オペラに、創作意欲を搔き立てられるのでしょう。
作者のメリメは、ボヘミア(スペイン)らしいエピソードとしてカルメンを描きたかったのかもしれませんが、読者の心はそれ以上にカルメンという女性に魅了され、逆に、カルメンを通して、スペインを見ているような気がします。
【まとめ】 メリメはフランス人
これも勘違いしている人が多そうですが、メリメはスペイン人ではなく、フランス人です。これほどスペイン文化や言語に詳しいのだから、生粋のスペイン人だろう――と思いきや、フランスのエリートで、1803年生まれ、ナポレオンの絶頂期から没落、王政復古や共和制など、めまぐるしい時代をリアルに体験した人です。同期に『赤と黒』で有名なスタンダールがいます。
メリメ自身、ヴァランティーヌ・ドレセール夫人という、美しい人妻と恋に落ち、創作においても多大な影響を受けました。「カルメン」も夫人との恋から生まれたと言われています。
ところが、メリメは、突然、夫人から絶交状を受け取り、二人の恋は終わります。メリメは深く傷つき、文学の傾向も大きく変わっていきます。ちなみに、ドレセール夫人の父親は考古学者で、弟のレオンは史跡保存官だったようです。それも「カルメン」の人物設定に影響しているかもしれません。
言い方は悪いですが、日本におけるメリメの立ち位置は「一発屋」で、カルメンだけが広く知られています。スタンダールのように『赤と黒』『パルムの僧院』『恋愛論』などが不朽の名作として知られ、「フランス恋愛小説の大御所」のように認識されているのに比べたら、メリメは「キャラクターのカルメン」ばかりが一人歩きして、作者自身はずいぶん影が薄いですよね。私も長年、スペイン人作家と思ってましたし(^_^;
それでも、作家としては、メリメの方がずいぶん幸福ではないかと思うこともしきりです。
なぜなら、「スタンダールの名前と『赤と黒』というタイトルは知ってるけど、主人公の名前は知らない(ジュリアン・ソレル)」というのと、、、
「『カルメン』というヒロインは知ってるけど、作者は誰か知らない。原作を読んだこともない」というのと……
「どちらが作家として幸福か」と問われたら、絶対、後者だと思うからです。
『赤毛のアン』のアンや、『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラも、そうですね。作者のマーガレット・ミッチェルは知らないけど、スカーレット・オハラがどんな女性かは知っている……という人が圧倒多数でしょう。
創作物でありながら、もはや歴史上の人物のように語られ、盛んに映画化や舞台化される。
作家として、これほど冥利に尽きることもないと思うんですよ。逆のパターンも多いので(作家の名前は知ってるけど、作品は読んだことがない。興味も無い)。
その点、カルメンの魅力は圧倒的だし、これほどいじり甲斐のあるキャラクターもありません。
ほんの100ページ(ドン・ホセとの恋物語は、さらに少なく、60ページほど)の間に、ちょろっと登場するだけなのに、「炎の女」「フラメンコ」「薔薇一輪」等々。人々の想像を搔き立て、今でも多くの女優や歌い手にとって憧れの役です。現代なら、キャラクターの使用料だけで、マンハッタンに高層ビルが建ちますね。
しかし、メリメの主眼は、「カルメンという女」ではなく、「バスク語の話者」「ロマ」の体現者としてのキャラクター作りにあり、マーガレット・ミッチェルが「こんな女を描きたい」と物語の中心にスカーレットを据えて、そこから物語を膨らませた手法とはずいぶん異なります。
あるいは、メリメにそれだけの計算がなかったからこそ、カルメンも物語の中から飛び出して、自由に歩き回れるのではないでしょうか。
映画に、オペラに、演劇に、大活躍のカルメンを目にして、一番驚いているのは、作者のメリメかもしれません。