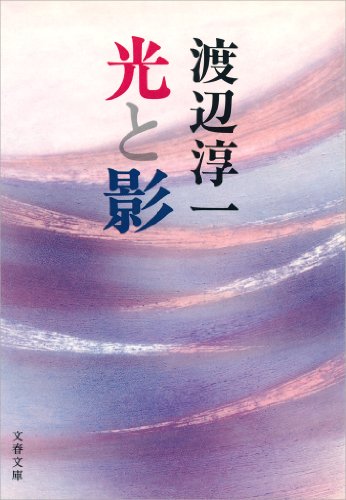渡辺淳一の傑作『光と影』について
あらすじ
西南戦争で戦い、共に右腕に重症を負った寺内大尉と小武敬介。どちらも東京教導団(陸軍の下級幹部養成所)の優秀な同期生だ。
症状は一刻を争うことから、同日、同時間帯に、右腕の切除術を受けることになった二人。最初に小武が手術台に上がり、次に寺内が運び込まれまた。
しかし、執刀医の佐藤は、続けて若者の腕を切り落とすのは不憫だ、ここは一つ、実験台になってもらって、温存療法に切り替えようと言い出し、寺内の右腕を残すことにする。
右腕を切断した小武は順調に回復し、寺内よりも先に退院するが、片腕をなくしたことから廃兵を余儀なくされ、「偕行社(かいこうしゃ)」という将校専用のクラブで働くことになる。
一方、右腕を残した寺内は、回復に時間を要しながらも、無事に退院して兵役に復帰。士官学校の指令副官に任命される。それから日清戦争で武勲をあげ、とんとん拍子に出世し、ついには陸軍大臣に任命。士官養成時代、能力的には寺内よりも優れていた小武は激しく心を乱される。
そして、いつの間にやら大臣の風格を身につけ、小武に対しても何やら同情的な寺内の態度に、小武はついに心がきれ、寺内につかみかかり、大臣室からつまみ出される。その後、寺内は栄光の中で天命を全うし、葬儀には皇族も参列、明治天皇よりお沙汰を賜るという名誉のきわみで、一方、プライドをおおいに傷つけられた小武はしまいに心を病み、誰に見取られることなく暗い精神病棟の一室で息を引き取る──。
将来を嘱望された陸軍大尉の小武は右腕負傷の憂き目にあう。偶然にも同じ傷で同期の寺内と病院で一緒になるが、小武は切断、寺内は腕を残した施術となった。廃兵となった小武はしだいに転落の気分を味わうが、いっぽうの寺内は……。カルテの順番という小さな偶然がわけた人生の光と影を、的確なタッチで構築した直木賞受賞作に、人間の皮肉を巧みに描き出した「宣告」「猿の抵抗」、若く美しい女に潜む戦慄をあつかった「薔薇連想」の三篇を加えた卓抜な作品集。
【作品の感想】 光と影が意味するところ
「人生そんなもの」と言ってしまえばそれまでだが、実際に敗者の側に立てば、そんなあっさりと割り切れるものではない。
「人生に勝ち負けなどない」「気の持ちようで幸せになれる」と言ってみても、人間の無念、やり場のない怒り、忸怩たる思いは、終生、続くのではないだろうか。
私が多分、(一時期イイと思った)自己啓発的な考え方──今ならライフハックとか癒しとかポジティブ・シンキングとか言われるものに抵抗を感じるのは、まさにこの部分なのだ。
確かに「幸福になる手段」として、人と比べないとか、自分を大事にするとか、明るく前向きに考えることは非常に大切ではあるけれども、一方、怒りや悲しみ、絶望や嫉妬といった心の闇もまた人間の真実に違いなく、悪いとされる方を切り捨て、自分で自分を「幸せ」と無理に納得させるような方法は、ある意味、自分に対する裏切りであるし、人間の本当の価値を歪めるだけではないか、と思うからである。
現代はあまりに「怒ること」「悲しむこと」「悔しいと感じること」「羨ましいと思うこと」などが「ネガティブ」の一言で片付けられ、周囲りに軽んじられるばかりか、自分自身でさえも否定し、見ぬ振りをする傾向が強い。
もちろん、愚痴や弱音ばかりの人は不愉快だし、自分でも暗いことばかり考えていると気が滅入ってくるものだが、それはネガティブな感情の活かし方や上手な表現の仕方を知らないだけであって、ネガティブな感情そのものが悪いわけではない。
問われるのは行動や表現の是非であって、感情はどこまでも内的な世界に過ぎないのだ。
そして、それを描き出すのが「文学」であり、本当の意味で文学的な役割をもった作品が書かれない、読まれない、というのは、知性、情操教育うんぬんの話ではなく、人間への理解が失われることである。理解がなければ愛情も育たず、結果、心地よい面だけがクローズアップされる。単純に「元気のいい人」「明るい人」「良いことを言う人」がもてはやされるのも、元を辿れば、人間理解の欠如によるし、本当に理解されるべきものはますます居場所を失って闇に追いやられる、悪循環である。
『光と影』は、影である小武の心にスポットを当てた作品であり、彼を「影の人」にしたのは、手術室に置かれたカルテの順番がたまたま「小武」→「寺内」であったこと、また寺内の右腕が切断されなかったのは執刀医・佐藤のその場の思いつきにすぎない。まさに運命のいたずらである。だが、兵役に復帰できなかった小武と、復帰が叶った寺内の明暗はくっきりと分かれ、能力や努力を超えた人生の不条理をいやというほど思い知らされることになる。
冷めた目で見れば、「たとえ右腕を切り落とさずに済んで、兵役に復帰できたとしても、果たして寺内より出世できたかどうかは疑問だよ」と言いたくなるが、そうは考えられないのが人の性だ。なまじ自分に過失や欠点がなかっただけに、余計でその気持ちが強い。
寺内の昇進を耳にする度、小武は思う。
小武は退役したからもはや階級は上がらないが、現役の寺内達が上がるのは当然であった。止まったままのものと進むものと比べるのが土台、間違っていた。そんな位階など忘れて、国のために尽くした勇士として対すればいいのであった。小武の現在がどうであろうと、寺内達が軽蔑したり見下したりするわけはなかった。まして寺内は悪気のない男である。だが小武はそう簡単に素直な気持ちにはなれなかった。
(かつてあいつは俺より劣っていた)
小武には下士官から尉官時代に寺内よりはるかに秀れていた、という自負心があった。兵術でも学問でも負けたものは一つもなかった。こんな男に絶対に負けるわけはないと思っていた。表面では親しい友人であったが、心の底では侮っていた。誇りが高かっただけに偕行社の一事務員としておめおめ出て行くわけにはいかなかった。
(二人を手術した佐藤医師との会話で)
「彼(寺内)はフランスに行くのですか」
「ご存じないのですか、閑院宮載仁親王殿下巴里御留学の補佐官に抜擢されて来月行かれるはずです」
小武は声を失った。何としたことか、寺内にだけ幸運がつきすぎてはいないか、小武は今も本を離さず偕行社の書籍という書籍はほとんど読み尽くしていた。学問も識見もともに誰にも負けない自信がある。独学だが洋書も読める。寺内が自分以上に洋書を読めるとは思えなかった。まして仏語なぞ上手に話せるわけがない。その男が宮様のお伴をして洋行するという。
(何かが狂っている)
小武は大声で叫びたかった。光と影の二つの方向に向かって歯車が少しずつ、しかしたしかに動き始めたようである。・・(中略)・・
自分にとって天命はあまりに不合理ではないのか、天命は不合理でいいのか、それでもなお従えというのか、寺内、お前のようにうまくいく天命ばかりではないのだ。お前は光に向かい俺は影になっていく。小武は再びやり場のない憤りにとらわれた。
今風のポジティブシンキングで言えば、「嫉妬があなたを苦しめるのです」「人と比べてはいけません」「自分を褒めて、今生きていることに感謝しましょう」となるのだろう。
だが、こうした気持ちに嫌気が差しているのは他ならぬ小武自身である。
そもそも、生き甲斐とか信念とかいうものは、揺るがないからこそ人生の基軸となる。その基軸を失って、そう簡単に気持ちを切り替えられるものだろうか。いや、それ以前に、人はそうまでして前向きであらねばならないものなのか。
世の中には最初の躓きから一生立ち直れない人もいる。
それを裁くのも人間なら、闇に光を当ててすくい取るのも人間だ。
そして、文学は、人が記憶の彼方に葬り去ろうとする闇を言葉に表し、光の中にすくい取ってくれる唯一の媒体である。
もし実在したならば、甚だ扱いにくい人物かもしれない小武も、小説の中では憎めない。現実社会では誰も言葉にしない胸の内を、小武はストレートに語って聞かせてくれる。そんな小武にほんの少しでも気持ちを添わせることができたら、世の中で無駄とか悪とかみなされることにも一分の理があることに気付くだろう。人によっては息苦しさを感じるかもしれないが、この息苦しさこそ、私たちが真に理解すべき痛みなのだ。
『光と影』は、誰にも責めることのできない人の世の不幸を教えてくれる。そして、それは文学ならではの体験なのである。
がん告知や末期医療に対する渡辺氏の死生観が色濃く反映された医療ドラマ。エロも楽しめる、一作で二度おいしい傑作。ちなみに筆者は渡辺氏と同じ考えです。告知はいたずらに患者を苦しめるだけで、死の恐怖に打ち勝てるのは少数です。(日本の場合)
渡辺淳一の本当の名作 ~『愛人』『化身』『わたしの女神たち』etc
渡辺氏は『失楽園』以前の医療エッセーや短編に良作が多いです。バブル期、サラリーマンの童話と称されたオトナの世界を堪能できる良作を紹介。