バレエ『瀕死の白鳥』について
《 瀕死の白鳥 》 ~THE DYING SWAN~
振付け : ミハイル・フォーキン
音楽 : サン・サーンス 「白鳥」 - 組曲「動物の謝肉祭」より
→ 音楽と子供の想像力が出会う時 サン=サーンス『動物の謝肉祭』(レナード・バーンスタイン)
マイヤ・プリセツカヤの『瀕死の白鳥』
本作では、死に瀕した白鳥が、生に向かって必死に羽ばたきながらも、ついには力尽き、死んでいく様子が描かれています。
ほんの二分足らずの中に、生と死のドラマが凝縮され、さながら、つかの間の人生を垣間見るよう。
『白鳥の湖』や『眠れる森の美女』といった大作に比べれば、一瞬で終る小品ですが、本作を踊るには技術以上のものが要求されます。
わずかな上演時間の中で、生への希求と敬虔さ、深い苦悩と悲しみ、絶望ではなく昇華としての死を表現しなければならないからです。
これまで多くのバレリーナがこの作品に挑戦し、それぞれの個性を生かした踊りを創出しました。
深い悲しみを表現するもの。
命の儚さを感じさせるもの。
倒れては起き上がり、ひたすら生きようとするもの。
実に様々ですが、筆者は、ロシアの偉大なバレリーナ、マイヤ・プリセツカヤが演じた『瀕死の白鳥』が一番好きです。
彼女が舞台の上で倒れるのは、たった一度だけ。
最後の瞬間まで、生きようとする強い意志に貫かれています。
バレエには、オデット姫やオーロラ姫など、美しいヒロインがたくさん存在しますが、マヤ・プリセツカヤの『瀕死の白鳥』は、ヒロインのイメージを超えて、強く、気高い『生の英雄』と呼びたくなるほどです。
ソ連の国営放送より
「Maya Plisetskaya Dying Swan」で検索すると、いろんな動画にヒットしますが、筆者が一番好きなのは下記の映像です。
日本でも、90年代後半、文藝春秋から販売されたVHSビデオに収録されていました。
ソ連時代のTV番組の録画で、たまに輸入盤DVDに収録されていますが、それもすぐに廃盤になる為、現在は非常に入手困難になっています。
上記の動画が再生できない場合は、別のUP主のリンクからも視聴できます。
Maya Plisetskaya - "Swan" https://www.youtube.com/watch?v=Krj-QsQvYSc
1992年の舞台
マリンスキー劇場で収録された『瀕死の白鳥』。
このとき、プリセツカヤは70歳。
「腕が動く限り踊り続ける」という彼女の言葉に偽りはありません。
意志があれば年齢など関係ないということが、ありありと伝わってきます。
創作の背景
今世紀最初のバレエ改革者ミハイール・フォーキンが友人のアンナ・パーヴロヴァのために、ほとんど即興的に振付けたといわれる小品。「瀕死の白鳥」といえば、パーヴロヴァ、パーヴロヴァといえば、「瀕死の白鳥」というように、作品と特定のダンサーの名が分かちがたく結びついている代表的な例である。
パーヴロヴァは大正11年(1922年)に来日し、帝国劇場でこの曲を踊ったが、曲が終わった後何分間も呼吸をとめたままだったという伝説がある。
パーヴロヴァは実際に白鳥をぺっtとして飼っていて、日常的にその動きを観察していたという。
フォーキン以前のダンス・アカデミックにおいては上半身よりも下半身に重きが置かれていた。
それにたいして、このバレエでは、下半身の動きはきわめて単純で、ほとんどパ・ド・ブーレ(小刻みに床を移動していく足の運び)だけで、反対に上半身の動き、とくにポール・ド・ブラ(腕の動き)に重きがおかれている。
パーヴロヴァは、下半身よりも上半身の演技力が優れていたといわれる。そうした彼女の特質を考慮して、フォーキンはこのような振付けにしたのだろうか。
いわゆるモダンダンスの創始者であるイサドラ・ダンカンの影響力が指摘されることもある。この作品が振付けられたのは、1907年のことだが、1904年、5年にダンカンがロシアを訪れ、フォーキンはその舞台を観て激しく感動したのだった。その感動が『瀕死の白鳥』の振り付けにも影響しているかもしれないのである。
一方、パーヴロヴァも、流れるような腕の動きはダンカンから学んだものだと語っている。
パーヴロヴァは、ある種の使命感のようなものがあったのだろうか、パリのような大都市の舞台に背を向け、小さな一座を率いて、一生涯、世界中を巡業して回った。そしてどこへ行っても『瀕死の白鳥』を踊ったのだった。だから、パーヴロヴァの縁起を超えることは不可能だと思われていたのだが、それでも、プリセツカヤ、マカロワなど、多くのバレリーナたちがこの作品に挑戦し、それぞれ個性的な白鳥を踊ってきた。
1992年に東京で開かれた世界バレエフェスティバルでは、ジョルジュ・ドンがこの作品を踊り、観客はそのあまりの美しさに息を呑んだ。だがドンが死んでしまった今、その舞台を見ることはもうできない。
マイヤ・プリセツカヤ MAYA PLISETSKAYA について
バイオグラフィー
マイヤ・プリセツカヤは、1925年、ロシアに生まれました。
芸術的血筋に生まれた彼女は、幼少の頃からその天性を発揮し、1943年、ボリショイ・バレエ団にソリストとして入団します。そして二年後には早くもトップに立ち、「白鳥の湖」や「ドン・キホーテ」といった大作のヒロインを演じて、大成功を収めました。
卓越した技術と表現力をもつ彼女は、古典のみならず、海外で活躍する様々な振付家と組んで、次々に新しい舞踊を創り出し、世界中の観客を魅了してきました。
彼女は今も舞台に立ち、素晴らしい舞踊を披露しています。
彼女はこう語っています。
「腕が動く限り、私は踊り続ける」と。
(執筆 1998年秋)
マイヤ・プリセツカヤは2015年、89歳で逝去されました。
マイヤ・プリセツカヤの名演
私が初めてマイヤ・プリセツカヤを知ったのは、有吉京子の傑作バレエ漫画『SWAN』の主人公、聖真澄と同じ。1970年代のボリショイ・バレエ『白鳥の湖』の東京公演がきっかけです。(参考 真澄の人生を変えた マイヤ・プリセツカヤの黒鳥とバレエ『白鳥の湖』)
プリセツカヤの東京公演は、NHKで中継され、子供心にも大きな感銘を受けました。
その後も、プリセツカヤのことが忘れられず、90年代、家庭用VHSの普及に伴い、上記の『瀕死の白鳥』が収録された名演集と、『白鳥の湖』のビデオを購入しました。
上述の通り、プリセツカヤの『瀕死の白鳥』は、いたずらに死を嘆くのではなく、最後の瞬間まで、生きようとする意志に支えられています。
そのひたむきな姿勢は、まさに生の英雄と呼びたくなるほどです。
現代も、「天才」「逸材」と称される踊り手は少なくありませんが、マイヤ・プリセツカほど意志的な強さと気品を感じさせるバレリーナはまたとありません。
あまりに早く生まれてきた為に、絶頂期の演技をデジタル処理された美しい映像で見ることは叶いませんが、こんな古い映像でも、抜きん出た才能が十分に伝わってきます。
ソ連の粛清時代、芸術家だった父を処刑され、母も強制収容所に送られたプリセツカヤにとって、踊ることは恐怖政治に対する抵抗でもありました。
彼女の舞踊を見る度に、芸術とは何か、人生とは何かを、考えずにいられないのです。
『ドン・キホーテ』のキトリ
アクロバティックなフィナーレが大人気の『ドン・キホーテ』(ミンスク作曲)
ヒロインの「キトリ」は、プリセツカヤの代表作でもあります。
会場の熱気まで伝わってくるような、躍動感あふれるキトリです。
キトリの登場。
キトリのソロも魅力的です。
ローレンシア
バレエ人生において、「一度もコールド・バレエを経験したことがない」というプリセツカヤ。
ボリショイ・バレエ団には、いきなりソリストとして入団しています。
若かりし頃のプリセツカヤは、身体を弓のようにそらし、踵が頭につきそうなぐらいのフェッテで、観客を魅了しました。
こちらも観客の興奮が伝わってくるような、情熱的なソロです。
『眠りの森の美女』 オーロラ姫
こんな可憐な役柄にも、彼女の意志的な強さと気品が表現されています。
クライマックスのアラベスクで軸足がぶれないのはさすが。
『バラの死』(アダージェット)
薔薇に取り憑いた一匹の虫が死へと導く情景を謳った、ウイリアム・ブレイクの詩『病める薔薇(The Sick Rose)』にインスピレーションを受けて、ローラン・プティがほとんど即興で振付けたという『バラの死』。(参考 → ウィリアム・ブレイク作『病める薔薇』 奈良教育大学英米文学教室)
音楽は、マーラーの有名な交響曲第五番・アダージェット。
ルキノ・ヴィスコンティの名画『ヴェニスに死す』の主題曲としても知られ、死を連想させる旋律が怖いほど美しい。
モーリス・ベジャールもジョルジュ・ドンの為に振り付けを手がけています。
参考 :
・ ウィリアム・ブレイク作『病める薔薇』 奈良教育大学英米文学教室(作品に関する詳しい解説があります。PDF資料なので、キーワード検索して下さい)
・ ウィリアム・ブレイクの詩とイラストの世界 『病気のバラ』
雑誌『音楽の友』に掲載
バレエに興味の無い人でも一度は見ていただきたいのが、マヤ・プリセツカヤの「瀕死の白鳥」だ。
わずか二分足らずの踊りの中に、人ひとりの人生を垣間見るような生と死のドラマが凝縮されているからである。
彼女の白鳥は、見る者に悲しみではなく、生きる勇気と喜びを与える。それは彼女の白鳥が、「死」を嘆きながら果てるのではなく、最期の瞬間まで「生」へのひたむきな想いに支えられているからだ。
力尽きてなお羽ばたこうとする白鳥の姿に、私は彼女の舞踊への情熱と不屈の意志を感じずにいない。
それはまた、悲しみや苦難を乗り越え、凛として生きてきた彼女の生き様そのもののように思う。
彼女は音楽に合わせて踊らない。
その腕の動きで、流れるようなパで、自ら音楽を奏でつつ踊る。
その音色のなんと切なく、美しいことか。
彼女の舞う空間には、いかなる弦にも作り出せない幽玄の響きが広がり、見る者を忘我の境へと誘う。
そして、その音色は一遍の詩のように美しく、力強く、心に語りかけてくる。
「生を愛せ、精一杯生きよ」と。
彼女の白鳥は死の踊りではない。生命の讃歌だ。
それは真に強く、気高い魂の持ち主だけが演じられる、「本物の白鳥」といえるだろう。
『音楽の友』95年五月号に掲載されたものを補筆しました。
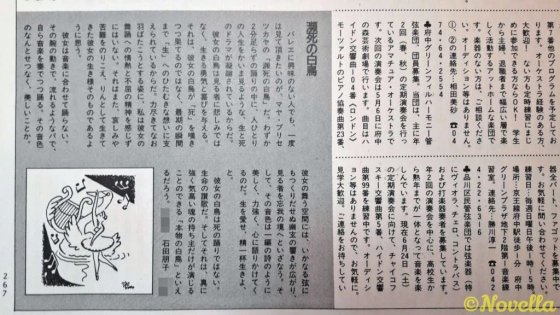
雑誌『ダンスマガジン』に掲載
「白鳥の湖」の特集、楽しく拝読させていただきました。
私が魅かれる「白鳥」は、なんといってもプリセツカヤです。
哀しみの中にも強さと気高さを秘めた白鳥(オデット姫)も良いですが黒鳥(オディール姫)も圧巻です。
彼女の黒鳥はまさに「邪悪の化身」、妖しい微笑と魅惑的な仕種で王子の心を支配していきます。
そして王子が過って愛を誓うと、勝ち誇るような笑いを残し、一陣の黒い風となって去って行きます。
演出により物語の結末は様々ですが、私はプリセツカヤが体現したような、愛の強さと美しさ、その勝利を高らかに謳いあげた彼女の「白鳥」が大好きです。
『ダンス・マガジン』94年12月号に掲載されたものを補筆しました。
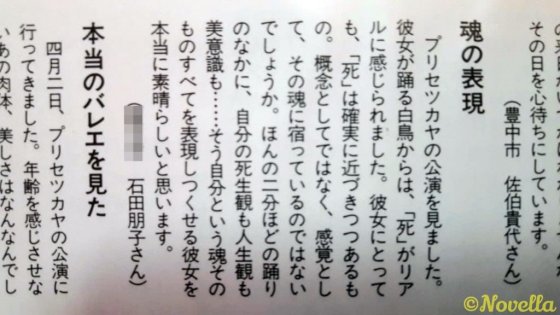
白鳥は永遠に ~マヤ・プリセツカヤの訃報に寄せて
記 2015年5月3日
娘の名前は迷わず「マヤ」と付けた。
『ガラスの仮面』の北島マヤも兼ねているが、それしか考えつかなかった。
なぜかと言えば、私にとっての芸術の起点はマイヤ・プリセツカヤだからだ。
*
今では「一芸に秀でる」という言葉も死語かもしれないが、芸術は人生を救う。
一つ才能があれば、それだけで人は生きて行ける。
成功、失敗に関係なく、才能とはまさに天の与えた給うた「人生の精髄」だからだ。
その強さと尊さを身をもって体現したのがマイヤ・プリセツカヤだ。
才能とは「ギフト(天からの贈り物)」。
決して粗末にしてはならないということを、私は彼女に教えられたのである。
*
21世紀に入ってからバレエファンになり、現代の優美で超絶技巧に長けたプリマの踊りと、プリセツカヤが60年代から70年代にかけて残した記録映像を見比べたら、恐らくその硬質な踊りに戸惑うのではないかと思う。
人によっては、「これが20世紀最高の踊り?」と疑念を抱くかもしれない。
それくらいプリセツカヤの踊りと現代のプリマは異なる。
何が異なるかといえば、前者はその人しか持ち得ない哲学や精神性が全身からほとばしっているからだ。
たとえば、彼女の白鳥(オデット)はたとえようがないほど高貴で意志的である。
悪魔の呪いという悲劇の中にあってさえ、何ものにも侵しがたい強さと貴さを感じる。
ただ身をよじって嘆くのではなく、それでも光を見詰めて生きようとする強さがある。
その愛もまた奇跡を待つのではなく、人間として対等だ。
終幕、オデットは王子と一体になって悪魔を討ち滅ぼすけれども、その意志的な踊りを見れば、「不屈」という言葉を文字通り体感するだろう。
それは舞台監督にすら手を加えることができない本物の個性──というよりは、舞踊家としての強烈な性である。
*
よく「信念をもって生きろ」という。
だが、信念は必ずしも人に幸福や平和をもたらさない。
それは時に闘いであり、孤独であり、試練である。
にもかかわらず、人が信念を有り難がるのは、本当の意味で強い人などこの世に数えるほどしか無いからだ。
多くは体制に負け、慣習に負け、不安に負け、世間に負ける。
信念は「個性」や「才能」といった言葉と同じ、多くの人にとっては「持った方がいい」という憧れに過ぎない。
だが、本当に信念に基づいて生きている人間にとっては、地獄の性である。
それ以外の何ものにもなれず、一生逃れることもできない。
だからこそ、一挙一動が周りとは違ってくるし、宙を舞うアームにさえ意志が表れる。
それはもはや「踊り」という次元を超えて、人生の所作としか言いようがない。
*
瞼を閉じれば、プリセツカヤの踊る『瀕死の白鳥』をつぶさに思い浮かべることができる。
ひとりぼっちの部屋で初めてあの映像を見た時の衝撃は今も忘れない。
幸せというなら、あれほどに素晴らしい踊りに触れ、なおかつ実際の舞台も何度も目にし、20代の多感な時期に寝食を忘れるほど夢中になれるものに巡り会えたことだろう。
最後まであんな風に踊り続けたことを信じて、今はただただ深い感謝と、娘にもかのように強靱な精神を身に付けてもらいたいと願うばかりである。

