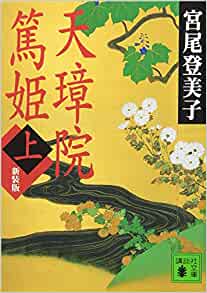宮尾登美子『天璋院篤姫』について
作品の概要
宮尾登美子の『天璋院篤姫』は、1983年から1984年にかけて日経新聞に連載された歴史小説です。
天璋院篤姫は、徳川幕府の十三代将軍・徳川家定に嫁ぎ、江戸城無血開城に協力した女丈夫で知られていますが、宮尾登美子の小説は、一人の女性としての内面にフォーカスし、徳川家の嫁として激動の時代を生き抜いた篤姫の志しや葛藤を華麗な筆致で描いています。
あっぱれな生き様 ~篤姫の物語
『篤姫』は、第13代将軍・徳川家定に嫁ぐため、故郷の鹿児島を旅立つ場面から始まる。
新幹線もなければインターネットもない天保の時代、鹿児島から東京に移り住むということは、海を隔てた異国に行くのも同じだった。まして将軍の正室ともなれば、自分の気持ち一つで里帰りするわけにもならない。
このたびの篤姫の旅立ちは二度とふたたび、この地を踏む日もあるまいと思える片道道中なのであった。
という気持ちは切実なものだっただろう。
そんな篤姫に、生みの母であり、当主・島津斉彬の養女となってからは、自分よりも格下になってしまったお幸の方は彼女の輿にひざまずき、形見となろうふくさ包みを手渡す。
女はいずれ生家を出るもの、と覚悟はしていても、こんなに遠く隔てられるとは考えてもいなかっただけに、篤姫はその包みを、お幸の方そのもののようにうやうやしく大事に、膝の上でそっとひらいた。
島津分家の一領主・忠剛を影から支えるお幸の方は、篤姫も心から尊敬する、賢くて情の厚い女性だった。
一人の母として娘の幸せを願うお幸の方は、当主・斉彬からの養女縁組みの申し出を知った時、夫である忠剛にしみじみと語る。
「そういたしますれば、敬子(篤姫の少女期の名)は定めし遠国へ片付くこともありましょうなあ」とさびしい思いも胸をよぎる。
領内にいれば、稀に往き来の日もあろうかと思えるけれど、知らぬ他国の大名の室ともなれば、今度城中に上がるのが今生の別れとなるのは間違いないことであった。
それに対して忠剛は、
「いたしかたあるまい。女子はどうせ生まれた家で死ねるはずもない故、死に場所はいずこであろうとそれは親の思い及ぶところではない」
そして、この事を知った篤姫は、斉彬の養女として江戸に行くことについて、『まるで勉学好きの男の子のように目を輝かせて』希望を語るのだが、
「これ敬子、江戸に出るとはまだ決まっておりませぬ。よしんば無事江戸に出られても、そなたの目的は輿入れですぞ。物見遊山ではありませぬ。この家で過ごすように気楽とは参りますまい」
とたしなめると、篤姫は素直に、
「はい」
と頭を垂れた。
賢いようでもまだ何も結婚の意味は判っておらぬと見える、とお幸の方はあわれんだが、また考えなおしてみれば、結婚前から誰がその中身の想像ができようぞ、とも思う。
そしてまた、生家を出て、島津本家に入る篤姫に、
「そなたはこれから教わらねばならぬことがたくさんある。女子は生家の家風を身につけたまま輿入れしてはならぬと申しますが、そなたの場合はそれがひとしお、きつうにいえましょう。
当家のことは一切お忘れなされ。何事もいわれたとことをようく守り、かまえて今和泉ふうを出してはなりませぬぞ」
とこんこんと言い聞かせる。
とはいえ、島津本家に入ってみると、衣装や立ち居振る舞いはもちろん、薩摩訛りにまで注意をされ、篤姫の悔しさや淋しさは半端ではない。生まれもったものを根こそぎ変えようとするお付きの者に苛立ちを覚え、時には堂々と反発してみせるが、やがてはその運命を受け入れ、『徳川の女』へと自らを立ててゆくのである。
しかし、篤姫の結婚は、決して満ち足りたものではなかった。
夫・家定は病弱な上に、精神的にも繊細で癇癪もち、彼女と床を共にしても指一本触れることなく、「将軍職などいやじゃ、いやじゃ」と涙を流すだけである。
今時ならこれだけで成田離婚になりそうだが、将軍に嫁いだ女は「夫がイヤ」というだけで離婚などできないし、床の事情を誰かに打ち明けることもできない。
だが、既に、自らの立場と運命をわきまえた篤姫はこう考える。
生涯連れ添うひとがいかなる欠陥を持っていようとも、それは嫁した女の運命であることを疑っておらず、それに篤姫は、父と兄三人の男子の弱い家に育っていれば、健康な女が夫を補佐しなければならぬという覚悟はしぜんに身についているものであった。
だが「将軍の世継ぎを生む」という大役を課せられた篤姫にとって、家定と正常な夫婦生活を営めないことは非常につらい現実だった。いつまでも懐妊の兆しのない篤姫を悪く噂する者もある。
そんな時も、
子に恵まれぬことを噂されたといっていちいち罰を与えていたら、この大奥にしめしはつかないし、また夫婦の寝室の秘密を明かすことなど立場上、金輪際できはしない。
と持ち前の賢さで乗り切ろうとする。
とはいえ、本物の夫婦として結ばれない淋しさは尽きることがなく、しかも、次期将軍の指名を画策するという島津斉彬からの密命もある。
このあたりの妻として、また一人の女性としての心情は、胸に迫るものがある。
だが、様々な人の思惑と立場が交錯する中、最初こそ、大恩ある斉彬の密命を真っ当することを第一に考えていた篤姫だが、自らの目で物事を見定め、島津家の養女としてより「家定の妻」であろうとする気持ちから、篤姫は次第に徳川幕府、しいては日本全体の利益を考えるようになる。
それはまた、篤姫が、よりいっそう「徳川の女」として生きる決意を固めた現れでもあった。
それゆえに、京都から輿入れした皇女・和宮との確執もいっそう深い。
とことん格式にこだわり、何かと言えば京風をもちだす「嫁」は、覚悟を決めて嫁いできた篤姫にとって、理解しがたい、というより、「実家依存症の甘えん坊」のようなものだ。
つい咎めたくなる気持ちを必死に堪えながら、この誇り高い嫁とどうにか打ち解けようと気配りを続ける。
そうした思いがようやく通じて、徳川幕府の危機の折には、共に力を合わせ、江戸城無血開城へと導く。
それから後は、島津家の援助もことわり、城を追われた徳川の人々の面倒を見ながら質素な生活へと身を落とすのだが、最後まで「徳川の女主人」としての誇りと賢明さを失うことなく、多くの人に惜しまれながらこの世を去った篤姫。
今時の女から見れば、「信じられなーい。イヤなら別れて、家に帰ればいいじゃーん」「援助してもらえるなら、してもらえばいいじゃーん。ムリしなくていいよー」という声も聞かれるかもしれないが、ある意味、退路を断ち、「ここが自分の生き場所」と腹を据える生き方は、なまじ逃げ道や他の選択肢に頼るより、よほど強くなれるのではないだろうか。
イヤになったら、離婚すればいい。
合わないと思ったら、別の道を行けばいい。
確かにそれが救いになることもある。
だが、一方で、心を弱くする。
「探せば、他にもっといいものがあるかもしれない」──そんな青い鳥幻想に振り回されて、結局、何をも成せぬまま終わってしまう女性も少なくないだろうから。
もちろん、篤姫のケースは恵まれた一例で、昔の女が結婚当日まで相手の素性も教えられず、親のひと言で強制的に嫁がされ、実家に帰ることも許されず、婚家では奴隷のように扱われ、「子なきは3年で去れ」とまで言われた、そういう史実を考えると、今に勝ち取った自由や能力は当時の女に比べればはるかに幸せに近いものかもしれない。
でも、自由や能力や権利より、もっと確かなものがある。
それは何かと言えば、心の強さだ。
自由で豊富な選択肢が心に隙を与え、能力や権利意識が男性(夫)との関係をこじらせるとしたら、それは必ずしも幸せの手段とはならない。
突き詰めれば、「幸せ」が「自分らしく生きた」という充実感であるとするなら、『貫く』ことが女の人生を豊かに磨き上げる。
そして「貫くこと」は、その他一切のものをあきらめ、退路を断つことでもある。
そういう意味で、篤姫は「あっぱれに生きた女」であり、今時の女にはそういう意気地があまりに足りないような気がしてならないのである。
【コラム】 与えられた運命の中で生き抜く
あれは30代になって間もない頃だったか。
自分の生き方に迷うことも多く、地に足が着かないというか、安らげないというか。
そんな時に知った言葉が、「女、三界に家なし」。
本来の意味は「女は三従といって、幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならないとされるから、一生の間、広い世界のどこにも安住の場所がない。女に定まる家なし」だが、しいては「あの世にも、この世にも、来世にも、女に『自分の家』と呼べるものはない」とも言える。
この言葉を知った時、一気に目の前が晴れたというか、さっぱりした気分になったことを今も覚えている。
「ああ、そうだったのか」と、私には非常に納得行く言葉だった。
これは旧時代の縛られた女の生き方を物語っているそうだが、現代風に解釈するとこうだ。
女の子も適齢期になると親や周りに「結婚は?」と聞かれ、実家住まいも「パラサイト」と言われて居心地が悪い。たとえ人並みに働き、収入のいくらかを家計の足しにしていても、実家に依存していると思われ、周りからも一人前とみなされず、「独身である」という一点で常に引け目を感じるようになる。
これが男性ならそこまで問題にならないのに、女性の場合は実の親からも遠回しに「出て行け」と言われ、いつまでも実家に暮らすことはできない運命にある。
結婚したら、したで、「嫁」と言われ、婚家の習わしや決まり事が第一になる。「自分の住まい」でもあるのに、「夫の家」「婚家のもの」という意識が強く、本当の意味で「自分の城」とは言えない部分が大きい。たとえ共稼ぎで、自分の収入からローンの一部を負担しても、周りには「夫の家」とみなされ、「自分の家」とは主張できない。なんだかんだで夫第一、婚家第一の暮らしがそこにある。
ようやく子どもも独立し、孫にも恵まれたら、今度は「老後」というものが大きくのしかかってくる。こうなると子ども世帯には厄介者でしかなく、場合によっては「嫁のひと言」で住処を失う。残る余生を子ども夫婦の機嫌取りに翻弄される畏れもなきにしもあらず。
このように、女性には本当の意味で「着地点」というものがない。
社会的、経済的に「自分の城」と呼べるものをもっても、どこかに弱みがある。
それは、その人個人の能力や精神力の問題、というより、『女性』とう立場に起因する。
『女、三界に家なし』。まさにそれが現実なのだ。女性がどう主張しようと、立場は簡単に変えられるものではない。
が、見方を変えれば、そうと腹を括れば度胸がつく。
これは今でも座右の銘の一つだし、ある意味、「退路を断つ」というのは思いがけないパワーを与えてくれるものだ。
「自由であること」は必ずしも女性を幸せにするとは限らない。
むしろ、与えられた場所、与えられた運命の中で、とことん生き抜くのも、あっぱれな生き方なのではないだろうか。