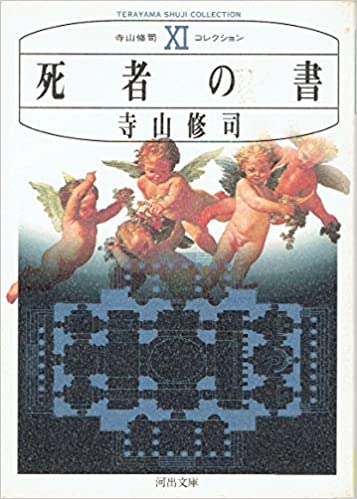ぼくはまだ人を殺したことがない。だが、そのことはぼくの名誉でもなければ、汚辱でもなく、ただ機会がなかったというだけのことにすぎないだろう。
ぼくの父は、殺人者であった。
<兵隊>という名の殺人労働者として戦場に狩り出されてゆき、ニューギニア諸島で何人かを殺した。
殺しの代償として貰った勲章は、父の死後、母が九州の炭鉱町へ酌婦としていくときに、質屋に入れた。殺人にも、株式と同じように相場があり、それは二十年以上前には安値だったのだ。
だが、今では誰も自分のしてきた殺人については語りたがらない。
大会社の応接間のソファに腰かけて、ゴルフ雑誌をめくりながら、次の日曜日を家族とすごすプランをねっている部課長たちにも、殺人の過去があったことを――それが連合赤軍の場合よりも、はるかに量的な殺人であったとしても――忘れたふりをしているのである。
だが、忘れたふりをしている殺人を思い出し、その状況下において引き金をひかねばならなかった自分の正当化にまで語り及ばない限り、連合赤軍事件を裁くことは出来ない。
長いあいだの、強迫観念じみた内的生活、単調な仕事、そしてようやく手に入れた、平和という虚構としてしか見ようとはしない。
時速百キロで、政治的先進から逃げて行き――過ぎ去った戦争も、すぐ近くまでやってきている死も、テレビや新聞を賑わしている日々の事件をも、虚構にしてしまい、批評し解説しようとする。
だが、習慣化を拒む事象のなかにこそ、真実は存在していたのではないだろうか?
ぼくらにとって殺人とは一体何なのか。
それがほんとうに「血の凍る」「悪魔の仕業」で、「顔をそむけたくなるような非道な」ことなら、なぜ人はそうした殺人の現場を見たがるのだろうか?
テレビで八時間ぶっ続けであさま山荘の殺人の中継を観つづけた数千万人の日本人は、「今にも起こるかもしれない、ほんものの殺人」を待っていた。こうした、「殺人を待つ心」の正規から始めない限り、いかなる日本問題も解明されることはないだろう。
高倉健は今日までにスクリーンの中で何人殺してきたか、。三船敏郎や勝新太郎や鶴田浩二は、永田洋子や森恒夫の何倍の人数を縛り、斬り、撃ってきたか。同じ行為がスクリーンの外へ持出された瞬間から<犯罪>化すると知っていながら、日本的英雄の原像がいつも殺人者だったのは何故だろうか?
あの灰色のブラウン管の中に長時間うつし出されているあさま山荘の銃撃戦は、一匙のコーヒーの共として観るものには「ただのテレビドラマ」にすぎなかった。しかし、テレビの画面でライフルを撃ちまくって茶の間の喝采をあびた板東国男も、つかまってしまうと「狂人」として扱われ、犯罪者にされてしまうことになるのだ。
虚構の中で、殺人者を英雄にせずにはいられない日本的現実の不幸と、虚構の外で殺人者として裁かれる革命家たちの不幸、二つの不幸のあいだを、浅間山の風は吹きまくっている。長い<冬の時代>は、当分のあいだ、眠るイノシシの目を醒ましそうには、ない。
ぼくは深沢七郎と二人で、テレビを観ながら対談していた。
「ぼくの考えでは……」とぼくは言った。「いま、殺人が容認されているのは、国家という単位だけなんです。国家は死刑という名の虐殺もできるし、戦争という名の大量殺人もできる。アメリカで、ベトナム戦争のマシンガン・ヒーロー(素晴らしい機関銃野郎)が殺した分の勲章をもらって引退し、ミネソタの農場へ帰ってきた。だが、百姓をやっても誰も英雄と呼んでくれない。それにくらべりゃ、ベトナムは最高だった。機関銃を乱射するたびに、新聞に写真が出たもんだ――ミネソタの農場で、だれにも相手にしてもらえない彼は、ある夜明けに、ベトナムでしたのと同じように機関銃を乱射して近所の人を皆殺しにした。そうしたら、忽ち逮捕され、アメリカ中の非難を浴びた。その男は「おれは同じことをやっただけなのに、場所が違うだけで狂人にされてしまうのか!」と刑務所の中でひらき直った。そうすると牧師が「あなたは、人間を殺したんですよ」と言った。「そうさ、おれはベトナムではそれをやって英雄になったんだ。同じことをやって英雄にされたり、狂人にされたりするんじゃ、あわないよ」。
このエピソードはぼくたちに物語るのは、国の中で殺すのはいけないけど、国の外へ行って殺すと英雄になれる、という倫理です。この倫理観に基づいて、連合赤軍の場合を考えてみると、彼らは日本の<現行の国家>を、国家として認めてない訳です。それでも、実際に起ってないことも歴史のうちですから、まだ出来上がってない幻想の国家も、国家として記述されなければならない。彼らはまだ出来上がっていない国家から召集された兵士として、敵国<現行の日本>の権力機構との戦争を引き受けた訳ですから、これは戦争として評価し、政治的専心をひきよせて論じなければならないと思うんです」。
ぼくたちが話しているあいだにも時はどんどんと流れていた。もはや、歴史はただの速度でしかなかった。ぼくはこの事件が事件として記述されるためには、マルクスが「ブリュメール十八日」で書いているように「歴史上の出来事や大人物というのは、いつでも二度あらわれる」のだ、と思わない訳にいかなかった。ただ、「一度目には悲劇として、二度目は喜劇として」かどうかは、わからない。少なくとも、二度目にあらわれるのが、ぼくら自身の呼び寄せによるものだとしたら、喜劇などにはしたくないからである。
ぼくは書きつづける。
「歴史について語るとき、事実などは、どうでもよい。問題は伝承するときに守られる真実の内容である。虚構であるゆえに他国であり、手でさわることのできない幻影である『過去』を、しばしば国家権力が作りかえて伝承してきたように、ぼくたちもまた、時の回路の中で望み通りの真実として再創造してゆく構想力が必要なのである」
私もしばしば「平和主義」とか「人道主義」とかいうものに懐疑的になる。
テロや内紛で市民が殺害されることは大変な罪に違いないけれど、テロの本拠地を爆撃して、幹部が死んだ、兵士が何十人と死んだ――という話になれば、正義として迎えられる。
あんな残虐な奴らは死んで当然、もっと爆弾を落とせ、皆殺しにしろ。
日頃、平和や人道に敏感な人も、心のどこかでその行為を容認して、雄弁な口をつぐむ。
批判したところで、他に方法など無いような気もするからだ。
でも、雲の上から平たく見れば、「死んでもいい奴(殺されて当然)」の線引きは誰がするのだろう。
市民を殺めるのも人間なら、「こいつは死んでいい」とジャッジするのも人間で、その判断基準になるのは何なのか。
それは常に絶対で、間違うことはないと言い切れるのか。
私たちはそれが『正義』と言われたら、訳も分からず従うところがある。
先日も『ヒトラー暗殺、13分の誤算』を観てつくづく思ったけれど、国民を洗脳するなど本当にたやすいことで、「明日から手数料は3%に値上げします」と言われたら、多くの人は、なぜそれが3%に値上がりするのが、2%ではなく3%なのは何故なのか、そもそも本当に値上げが必要なのか、深く考えることもなく、「まあ、30円ぐらいなら、いいか」と受け入れるようになるだろう。その積み重ねで、3%が5%になり、5%が7%になっても、多くの人はぶつくさ言うだけで、「また値上げか」と、値上げ自体に馴染んでしまい、抗うこともなく、疑うこともなく、結局は受け入れてしまうだろう。そんな風に、国家が大きく舵を切っても、多くの人はその不自然に気付かないし、いつでも過激な思想に染まっていけるものなのだ。実際、某地を爆撃するのも「当たり前」の感覚になってるし、悪い奴を一掃したらそれで終わり、その向こうにある真実――いったい誰がこのような悪人を生み出し、本当はどのように解決すべきだったのか――など、考える機会も、疑うこともなく、戦争の罪にも馴染んでしまう、というのが現実ではないだろうか。
真に憎むべきは、もっと別の所にあるのに、分かりやすい構図の中で、一方的に事が進み、知らぬ間に決着がついている。
これらの罪を後押ししているのは、庶民の鈍感であり、無関心であり、世界の激変には敏感だが、日常的な変化は案外すんなり受け入れてしまう、同調性なのだけども。
そして、多くの庶民には裏に潜むものは見えない。
誰かの解釈を「そうなのか」と受け入れるだけだ。
ニュースしかり、解説しかり、歴史しかり。
時々、自分の地場を離れてみると、よく分かる。
そこで「正しい」とされているものの、歪みや違和感が。
だが、それに気付くには、「疑う」という勇気が必要だ。
そして、多くの場合、人は真実を直視する勇気より、いつもの日常を選び、「何かおかしい」と感じながらも、破滅に向かって、まっしぐらに走っていくのだろう。
時に、百万人単位で。
- 戦争とは歴史の無慈悲なロシアン・ルーレット 映画『ディア・ハンター』
- 悪の凡庸さ 映画『ハンナ・アーレント』 自分は過たないと言い切れるのか
- 映画『アイヒマンを追え』 なぜ戦犯は裁かれねばならないのか ~歴史と向き合う意義
ベトナム戦争に従軍した青年兵士の心の傷を描く傑作。
「命令されたから、やった」平凡な小市民が残虐な戦争犯罪に加担するまでの過程を追及した歴史映画の傑作。
戦争が終わると、ナチスの残党は一般社会に溶け込み、普通の庶民として暮らしていたが、なぜ戦犯は裁かれなければならないのか、理由が克明に描かれている。
初稿:2017年3月7日